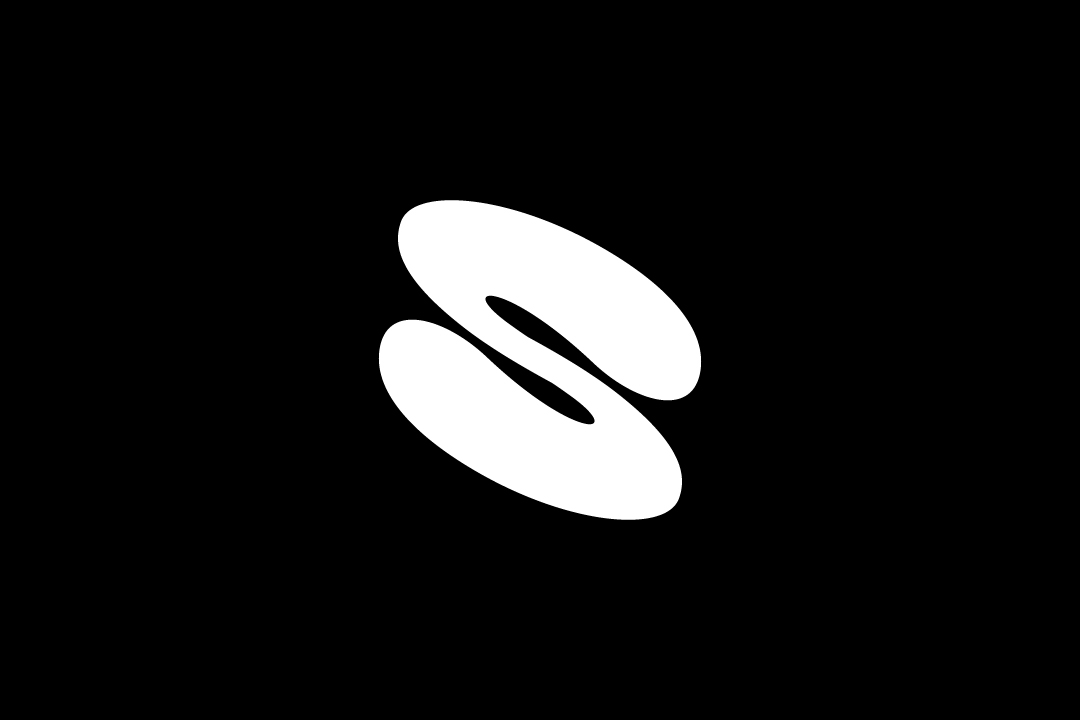月曜日、手紙が届く。
わたしはプールサイドで休暇を過ごしている。プールは正方形でとても深い。
へりはざらついた白だ。ほとんど黒に近い濃い青色で『水深15M』と描かれている。でもわたしのいる寝椅子のうえから見えるのは光を反射して揺れる水面だけだ。
手紙は銀の盆にのせられて運ばれてくる。音もなく一礼してうやうやしく去ろうとする若い男を呼びとめて訊ねる。あの、すみません。このプールって本当に十五メートルもあるんでしょうか。
男はわたしの視線を追い、慇懃な身振りで振りかえる。ええ、そのように設計されております。礼儀正しく節度ある笑顔。
それって、とわたしは思う。それってもっと深いかもしれないしもっと浅いかもしれないってことですよね、十五メートルって描いてあるからそういうことになってるだけで。思うだけで口には出さない。別に正確な深さを知りたいわけではないのだ。
笑顔を保ったまま、少しのあいだこちらを見つめたまま男は待つ。わたしが何も言わないのを確かめると会釈して行ってしまう。乾いた足音が響く。規則正しく抑制された歩調。
サイドテーブルに置かれた銀色の盆は大げさでかえって安っぽく見える。薄い水色の封筒をうら返す。ここから8949㎞離れた墓地の管理会社から届いたものだ。
死んでから過ごす土地を購入するのは思ったよりずっといい気分だった。生きている間に死後の住まいを決める。それだけのことがわたしを不思議に安らいだ気持ちにさせた。
気がかりだったのは遺体のことだ。遠方からどうやって墓までたどりつけばいいのか。なんといってもわたしは墓地から8949㎞離れた場所に住んでいるのだ。
封筒をひらく。薄青い便箋にタイプされた青い文字が並ぶ。簡単な挨拶と礼のあとに、「遺体は小包で郵送、遺灰はFedExで送付が可能です」と書かれている。ご安心ください、ぜひお任せください、という結びの言葉にすっかり安心して寝転がる。
白い板の貼られた天井は高く、斜めにさし込んだ強い光で明暗に区切られてくっきりと線ができている。ふと風が吹いて甘い香りがただよう。
壁際に置かれた鉢からのびた亜熱帯の植物の分厚い葉がゆれる。白く小さな花びらが散る。スピーカーから流れはじめた音楽は水音と反響でほとんど聞きとれない。大きなファンがゆっくりと回り、生ぬるい空気を撹拌していく。
火曜日、陽射しはあいかわらず眩しい。
浜辺ではパーティーが開かれる。休暇を過ごす皆に招待状が届く。
床から天井のうえの方まで、一面にガラスの嵌められたプールの窓からパーティーが見える。空、海、白い砂浜、緑の芝。窓の外の景色は発光している。時折海鳥かなにかが空を横切る。
テーブルを囲む人々。談笑の合間になんども乾杯がくり返される。黄色や水色のあざやかなサンドレスを着たご婦人に一時もじっとしていられない子どもたち。赤ん坊を抱いた若い父親。身につけているのはショートパンツだけで、日に焼けた背中がむき出しだ。
天幕の下、ちいさなブースでDJがレコードに針を落とす。音楽がかかる。果物や花のあふれた器が運ばれ、色とりどりのカクテルがふるまわれる。グラスがたおれると人の輪がくずれて嬌声があがる。こぼれた酒が砂を赤く染める。
やがて夕暮れが訪れるとはりめぐらされた電飾がつぎつぎに光を放つ。テーブルに置かれたたくさんのキャンドルに火が灯る。腕時計に首飾り、眼鏡に哺乳瓶、揺れるイヤリングが、ラメで塗られた爪が、身動きするたび砕けたガラスのようにきらめく。浜一面に散らばった大小の光が明滅する。まるで星空が地上に落ちてきたみたいだ。
わたしはパーティーに行かない。プールサイドから眺めるだけで充分だ。もちろんここにも山盛りになった果物の皿と細長いグラスに入った酒が届けられる。つやつやと赤い苺を口に含んで炭酸のきいたカクテルを飲んでいると、皆と一緒にパーティーに参加しているような気分になる。
ちいさな仮設ステージでは妻を亡くした男がマイクを握っている。スピーカーから流れるのは過ぎ去った妻との日々の思い出の曲だ。歌声はなんどもとぎれる。下を向いた男は片手で顔をおおう。隣に立つ幼い息子が彼の手をとる。
さんざめく浜の向こうで黒い海がうねる。
水は墨を流したように黒く、全ての光を吸いこむ。あまり見つめていてはいけないのに目が離せない。
いつか波が黒々と浜にあふれて皆を飲みこむ。その腕はどこまでも伸びていく。プールの窓を破り、床のタイルをおおい鉢をたおす。寝椅子ごとわたしをさらう。なにもかもが海の底にひきずりこまれる。
水曜日、光がかわった。
朝の浜はうってかわって静かだ。
宴の気配はあとかたもない。われたグラスもこぼれた酒も、ちぎれた真珠もしおれた花も、なげすてられた果物の皮も魚の骨も、きれいにかたづけられてどこにも見当たらない。忘れられた黄色い薔薇が一輪だけ波打ちぎわにのこされている。
あれは本当に昨日のことだったろうか。夢だったのかもしれない。かつていつかどこかでパーティーがあったことは確かなのだから、それが昨日でなくても、ここでなくても、べつにかまわない気がする。
わたしたちは時計ではない。赤ん坊のころはじめて聴いた音楽の思い出を反芻するうちに時々の記憶がまざりあってもそれとはわからない。いずれにしろわたしにはもうよくわからない。
あまりにも多くの時間がわたしのうえを過ぎていった。心も体もなめされて、やわらかくまるいあいまいな輪郭だけがここにいる。ずいぶん長い間なにかを待っているようにも思うが、なにを待っているのかはさだかではない。
午後になって急に日が翳った。窓の外、薄墨色の空のした、右から左へと管理人が歩いていく。
足どりは確かだ。ときおりかがみこんではなにかを手にとり調べる。立ち上がってまた歩き出す。どこに行きなにをすべきかわかっている人間特有の迷いのなさだ。
やがて向きを変えてこちらへ近づいてくる。小鳥ほどの大きさのものを左手に持っているのが見える。
管理人によれば、この一年で三十七つの足首が浜辺に流れついたのだという。
それはいつもと変わらないある朝のことだった。いつものように浜に出ると足首が落ちていた。男物のサンダルを履いた右の足首だ。先を急ぐだれかが足ごと脱いでいったように白い砂のうえに転がっていた。
六日後の朝、おなじ場所でふたたび足首を見つけた。今度は左足だった。最初のものよりひと回り小さくほっそりとして、足の爪は真珠色に光っていた。若い女の足に違いないと管理人は思った。
浜には次々に足首だけが流れついた。毎日のように見つかるときもあれば、ひと月も見ないこともあった。管理人は海辺の家に庭をつくり、足首が流れつくたびにそこへ埋めた。
左足のことも右足のこともあった。老いた足も幼い足もあり、老いてもおらず幼くもない足もあった。足首ではなく膝から下のものもいくつかあった。足首は世界中からこの浜辺にやってくるようだった。
毎日つけているという日誌を見せてもらう。几帳面な文字でこう書いてある。
男の右足首、一つ。革のサンダル。
女の左足首、一つ。真珠色に塗られた爪。
子どもの左足首、一つ。黒子が三つ。
老人の膝から下、一つ。脛に傷。
手にあたらしい足首をささげ持ち、管理人は日誌の一番新しいページを開く。男の左足首、一つ。甲にタトゥー。そう書きつけてプールへと歩いていく。しばらく水面を眺めてから顔をつっこむ。そのまま長いこと動かない。生きているかどうか心配になるころようやく顔をあげる。何にもいないね、と大きな声で言う。髪から水滴が垂れる。床が濡れてそこだけ色が濃くなる。
間違いないよ、鮫も足首もなあんにもいない、もう一度言って顔をぬぐう。声は天井にはねかえり、実際よりずいぶんおおきく聞こえる。
管理人は長居しない。手をふると足早に去っていく。とても忙しいのだ。浜辺はどこまでも続いている。見て回らなければならない場所はいくらでもある。それがどれほど大変な仕事かわたしには見当もつかない。
行ってしまうと急にしずかになる。眠気がわたしと世界を遠ざける。わたしは足首の持ち主のことを考える。足首をなくした体のことを考える。手をのばして自分の足首にふれてみる。ひんやりと冷たい。ずっと座っていたせいか感覚が鈍い。他人の足をさわっているみたいだ。
木曜日、父が訪ねてくる。
訪ねてくるというのは正確でないかもしれない。わたしには目もくれない。こちらのことは見えてもない様子だ。
はじめはプールだった。父は前ぶれなくあらわれた。
水面がこまかく揺れ、生き物みたいに泡立ったかと思うと黄色いシュノーケルの先が見えた。ついでまだ黒い頭髪と髭、大きなゴーグルをつけたとがった鼻が出てくる。口から水を吐き出すとへりに両手をかけてぐっと体を持ち上げる。
痩せているころの父、今のわたしより若い父だ。顎先から水をしたたらせ、筋肉質の手足を伸ばしては縮め、苦もなくプールサイドへ上がってくる。黄色い足ひれをつけている。
目の前をとおりすぎて壁の蛇口をひねる。シャワーから水が勢いよくほとばしる。飛沫がはねて冷たい。両手で全身をこすり、水が止まると首をかしげて耳の水を抜く。両手を頭のうえで組みのびをする。足ひれをはずすと外へと歩いていく。
ながい手足も、歩きながら肩をすくめる仕草も、真顔なのに笑っているように見える口元も、みんな父のものでまちがいない。
追いかけようと思うがうごけない。
子どものころ今と同じようにプールサイドで待っていたことを思い出す。どうして忘れていたのだろう。
あのころ、危ないからという理由で子どもがプールに近づくことは禁じられていた。プールサイドの寝椅子のうえがわたしの定位置だった。
あおむけになって目をとじる。空調のブーンという唸りが聞こえる。プールは静かだ。いましがた父が潜っていったなんて信じられない。
胸いっぱいに息を吸いこむ。水を蹴って体をねじり、深い水の底まで潜っていくところを想像する。だんだんくらくなる。音が遠ざかっていく。光が消える。なにも見えない。自分の心臓の音しか聞こえない。
ふたたび父が水から顔を出すまでの間、わたしはいつもとちがうところにいた。はてしなくながい時間が過ぎた気がしたのを覚えている。
父は行ってしまう。プールからあがりシャワーを浴び、浜へと出ていく後ろ姿が遠くなる。待って、と呼ぶ声も届かない。濡れた足あとが点々と床に一列の染みをつくる。
若々しい背中が見えなくなる。ようやく動くようになった足でプールへと走る。顔をつっこんで目を凝らす。だれもいない水の下、よく知っている体が見える。足首をなくしたわたしが沈んでいく。十五メートル。差しのべた手はとどかない。呼びかけようと口を開くが言葉は泡になって消えてしまう。
金曜日、火が焚かれる。
浜辺に巨大なやぐらがくまれ、白い布の包みが運ばれてくる。包みは大きい。左右に二人ずつ運び手がつく。
包みはやぐらの天辺に置かれる。風が吹くとはためき、いまにも飛び立ちそうに見える。大きな白い鳥が翼を広げたみたいだ。
布のうえには南国の花で編んだ冠が載せられている。やぐらの周りにも赤や黄、白の花びらや米が撒かれる。日没が近づくと松明をかかげた女が幾人もあらわれてやぐらへと火を移していく。
燃えさかる火を囲んで人が集まる。キャンプファイヤーのようだ。ぱちぱちと爆ぜる音だけが聞こえるなか、参列者たちは一人また一人と輪の中に進み出る。
土曜日、トラックが停まる。
白い車体に紫とオレンジの派手なロゴ。FedExのピックアップだ。
集荷係が降りてきて荷物をつみこむ。日差しが眩しい。今日も暑くなるだろう。
週末にはまたあたらしい客がやってくる。風にゆれる花から甘い香りが漂う。パーティーが開かれ音楽がかかり酒がこぼれる。水はあふれ流れてはめぐりいつか還る。
それがいつのことかは、きっともう思い出せない。波の音だけがいつまでも聞こえている。