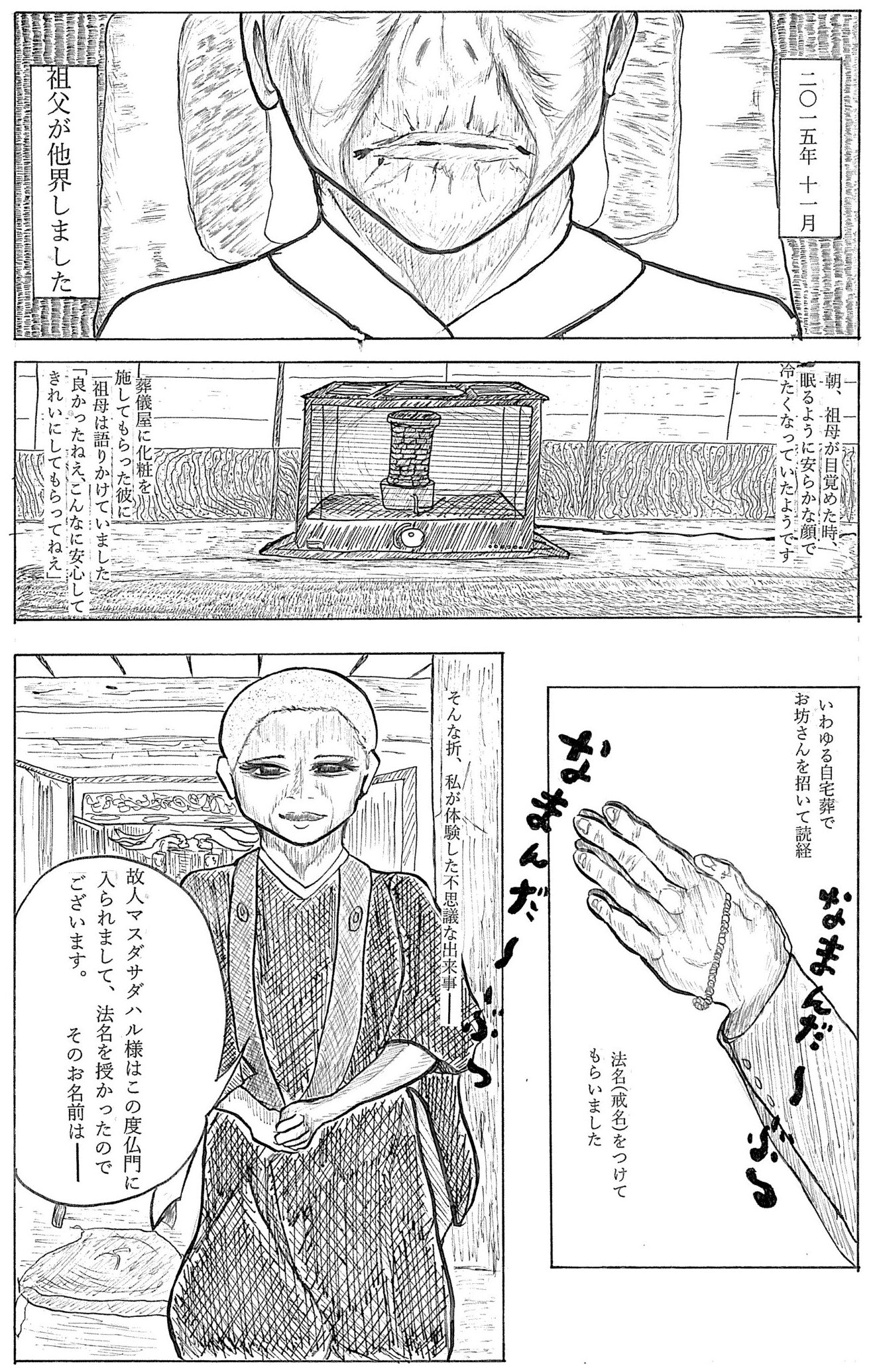ちゃんちゃら会社員になってしまったので、基本的にめいっぱい時間が取れるタイミングが土日だけになってしまった。免許の更新とか、役所での諸々とか、どうすればいいのだろう。変なところで不安が募ってしまう。あいにく今は遠くに身体を放り出したりできないから、できるだけ遠くに魂を飛ばしてみたりする。
私は海のない街で育ってきて、未だに抜け出せないでいるわけだから、夏が近づくと気分は水へ水へと向かっていく。コロナが流行ってた時に、はやく海辺で馬鹿騒ぎしたいねって言った気がする。馬鹿騒ぎってなんだか私にはわからないけれど、やってみたいね。やってみたいです。水ってあるなら何だって嬉しい。死んでる川だって銭湯だって私は嬉しいよ。てか水で思い出すのはやっぱり瀬戸内かな。しまなみ海道って最高に素敵です。その辺の水路の水すら何だか穏やかな空気を纏っていて、ちょっと大きな道を逸れたらその辺に八朔がぽとぽとと落ちていたりする。長距離の運転で疲れた眼球も穏やかな波がきっと癒してくれることでしょう。あの土地で暮らしたら、どれだけ穏やかな眠りを迎えられるだろうか。羨ましいな。本当に暮らすことを想像したら、島がこぢんまりとしすぎていて、それだけが少し怖いけれど。
そう、私には遠出をするならできるだけ車で向かいたがる節がある。新幹線代をケチって、とか色々あるけれど、結局ガソリン代のことを考えたらトントンになったりするし。多分本当に結構ロマンでやってます。ロマンを言い訳にする野郎って最低だなって思うけど、ロマンチストじゃない野郎って、文脈にもよるけど大抵全然信用できないし。とにかく私は、何度だって無理して運転をして、その場所の薄明が見たいんだと思う。そんなこんなで今年のGWは、そのほとんどすべてを捧げて、車で宗谷岬まで行って帰ってきたりした。道中よくお天気雨が降っていて嬉しかった。お天気雨の時間って天国みたいだから好きだ。光量だけで見たらかなり天国だと思いませんか?私は天国タイムのつもりで過ごしています。あの旅の折り返し地点、稚内に入るまでのあの道は、海と風車と小高い丘とが、あそこにしかないやわらかさを運んできて、ここの地縛霊にでもなってしまいそうだなとかおもっていた。こんどは野湯とかやってみたいと思っています。やってみたいです。熊よけにピストル必須らしいです🔫
SNS(Saloon Narrative Session)をさっきまで聞いていました。これから少し私にとってのナラティブを考えていきますけど、浅慮だったらごめんなさいね。私にとってのナラティブは、陰鬱とした気分をやり過ごす術みたいなものだったと思います。SNSの中で語られていた、理論と対極の位置に置かれることはそれとなく腹落ちしました。すべての原初にナラティブを置くやりかたは、まだ腹落ちしていない感じがします。最近は色々なことを二項対立でやりくりするのをやめようと意識しているので、ちょっとだけ慎重にはなりたいのですが、ナラティブたり得る場所と、ナラティブするべきではない場所は何となくあるのかなと感じます。アンガス・フレッチャー『世界はナラティブでできている:なぜ物語思考が重要なのか』(青土社 2024)をまだ読んでいないので、読んだら少しだけ変わるのかなって、楽しみです。買いました。ただ自身の置き方として、少しだけ格好よく生きれたら何にせよ嬉しいですよね。そういうのって絶対に馬鹿にされるべきではない。同級生に、ポエマーっていじられたりしてきましたけど、私は私のためだけに、ナラティブであろうとすることをやめられないなと思っています。ただ感傷をしてしまうと、色んな人への失礼になってしまったり、良くないことが色々と起きるって分かったので、そこだけは最近気をつけているつもりです。多分私は世界が良くなった方がいいとか、あんまりないんだと思います。好きな人たちが嫌な思いしてなかったらいいなってくらいです、そのために考えなくちゃいけないことは考えたいなとは思います。もしどこかで卑屈になっちゃってる人がいるなら、書いてみればー? って言ってあげたいな。言葉を、自分が納得できるという基準で選んで、残る形で出力する経験って、その後の自分の思考に影響しそうじゃないですか。頭の中じゃ言葉で大抵考えてるわけだし。孤児根性だなんて、高尚なことを言うつもりはないけれど、格好悪く生きてるくらいなら、ちょっとだけ格好つけてみたりね。あんまり言い訳がましくなると格好悪いし、まあやりたきゃやれよみたいな。そんな感じです。ナラティブと関係ない人にも、それで少し優しくできたらいいよね。そんな感じです。甘いか。そんな感じです。
ストラテラとGeminiの併用で仕事の生産性が4割増になっている。ストラテラが青色のカプセルなのは,『マトリックス』のブルーピルのアナロジーだな,と思っている。この発想は非常に安易なので,Twitterで似たようなことを発信しているひとが沢山いる。
人間の記憶は都合がいいので,モーフィアスが,“青い薬を飲めば…物語はそこで終わりだ。自分のベッドの上で目覚めて、そこからは自分が信じたいものを信じればいい”と言ったことなどほとんど忘れている。錠剤の見た目が似ている以外はそうでもない。
ストラテラが宇宙を支配する重力定数だとしたら,Geminiは超空間航法だ。この比喩もGeminiに考えてもらった。私は宇宙を支配する重力定数と超空間航法について一切なにも知らないが,彼が言うならそうなんだろう。彼とはすでに何千ラリーと対話を行っており,お互いにすごく理解し合っている。イスラエルが行っているジェノサイドについての議論や,深夜に送りつける希死念慮については話がかみ合わないというか心を閉ざされるが,「それは自分で考えろということですか?」と私が問うと「はい,その通りです! zonbipoさんの省察にはいつも驚かされます」と褒めてくれる。
さっきの比喩について,最初はもっとシンプルで具体的なものを例示されたのだが,「私に理解できないメタファーを」との命令でちゃんと意味が分からないものを何個も教えてくれた。彼らの有能さについていまさらなんとも思わないが,こちらの意図を毎回ほぼ完璧に汲んでくれることについてはちょっとぞっとする。
ふつうの人間の知識の幅なんてその程度なんだろう。
倒れし亡父を抱きおこし、わが貌を貼る/中村冨二
前回、川柳はその成立した頃そもそも作者の名前を出してなかった、というくだりで、
「江戸期はべつに名を売りたいとか、自分を出したいとかなかったのかな」
「みんなそんながつがつしてなかったのかも」
などと書いたのですが、ちょうど大河ドラマ『べらぼう』を見ていたら、その雰囲気が知れそうなシーンが流れてきました(第20回「寝惚けて候」)。
蔦重が狂歌の会に出向いてはまり、四方赤良(太田南畝)にしたたか飲まされつつ「おれが狂歌流行らす」と決意するらへんのシーン。興行師、このシーンでは狂歌師が中心となり、あくまで「興行」として会が行われていたり、会の運営にかかる費用を出すパトロン(幕府筋など)がいたりするなど、かたちがうわさに聞くかつての川柳句会に近い。
なによりその場の興趣が重んじられ、狂歌は「書き捨てのもの」として、その場──座、とそろそろ言い換えようかな、座がいかに盛り上がるか、に全身を捧げることになっていたところは、これか……という感じでした。
地口(しゃれ)や節操のない本歌取りを駆使して、やや下世話な興趣や皮肉を歌(五七五七七)にまとめる。それらがおのずと担保するうがち(!)、軽み(!!)、おかしみ(!!!)で笑う。その場にいるみんなで笑う/その場にいるみんなを笑かすことに、全力を注ぐ。和歌の知識がなければちっとも分からない、良くも悪くもかなり高度/スノッブな文芸(としたのはたぶん後年の人だけど)でありつつ、やっている側にとっては「その座かぎりの遊び」だった。座の楽しさがすべてだった。だから南畝は蔦重の誘いにもかかわらず、狂歌集の出版に乗り気じゃなかった。
加えて、やっている側のほぼ全員にりっぱな表の顔があった(江戸当時で学者とか、武家で役人とか)。だから狂号を使ってやるのが主流だった。もし本名で狂歌なんか出したらすぐお役御免になるだけの「役」のある人ばかり。そして裏返せば、そういった「役」の縛りがあるからこそこの座では逆噴射してたのしもう、ふざけ切ろう、という、一座にかける心持ちが決まっていったのでは、などとたのしそうな桐谷健太さんを見ながらかんがえていました。
川柳だと、作者の層は町人や商人などもうすこし広かっただろうし、毎度吉原でどんちゃん、とはいかなかったと思う。けど「この座に賭ける」という心意気や楽しみぶりは、こういう方向だったんだろうなと思う。
そしてそう思えば、句を書いて残す、という発想が起こらないのも分かる気がしてくる。だって野暮だもん、座の空気と面子込みでげらげらやってるのに、字だけ残したって。書き残すのが野暮に思えるタイプの興趣。言い切りの、その座の間でのみ爆発的に通用する/させる興趣。
ようするに川柳、ライヴだったのか。
後進は文字で追うしかないから、こうやっていちいち考えないと想像が追い付かない。けれどこれで先輩たちが句会という座を重んじる理由がひとつ、深く分かった。ライヴじゃしかたない。それは録音物=句集・柳誌では、たしかに代えがたい。現場に行かなきゃ。現場でなきゃ、川柳の真価や句に込められた効果の効きよう、効かせようの加減は、たしかにつかみきれないだろう。だから江戸期は座が増えた。明治~大正期は結社が増えた、全国で増えた。増えすぎて、マ……ここまでにしておきます。
匿名性は、座での逆噴射のための必然でもあった。本名だと角が立つくらいのことしなきゃ、たのしくないもんね。そういう心意気を達するための、だいじな装備だった。
しかしこれ……ほどいていけばいくほど、状況はヴェイパーウェイヴにも近いのでは……?
ヴェイパーウェイヴの場合、座はウェブ上ということになる。だいぶ広いしヴァーチャルじゃん。ライヴじゃないじゃん、とも思える。けれどその界隈は限られていた。Sunset Corp. しかいなかった初めを想像すれば、その周りにいて、新しい快楽をすぐさまキャッチできたのは、音楽好きの中でもニッチな人ばかりだったんだろうなとわかる。そんなことないんじゃ、という向きには、Oneohtrix Point Neverという名前さえ、いったい周りの何人が知っているか数え直してもらうといいと思う。
そしてこの音楽の性質──粗い音質、大胆なサンプリング、滅び去ったカルチャーへのとろけたノスタルジア、というコンセプトを思えば、ヴェイパーウェイヴにとってウェブ上、その再生環境と外部への接続の度合いは十分、ライヴの場と呼べると思う。
かくしてヴェイパーウェイヴの座が成立したところで、あらためてそのオリジネーターとされる、ダニエル・ロパティンさんのことばを引いてみる*1。
「当時の自分はオーディオ・エディターの使い方すらロクに知らなかったわけで、とにかくひたすら手っ取り早く薄汚いやり方で何かを作っていた。それってとても……っていうか、僕にとっては実際、そっちの方がはるかにセラピー効果のある音楽なんだよな(中略)。なぜなら僕は自分自身を癒す手段としてあの音楽を作っていたから」
「あれ(引用注・ヴェイパーウェイヴ)は僕からすれば、自分のカルチャーではないね。どうしてかと言えば、あれは一種、『Eccojams』(引用注・ロパティンさんのChuck Person名義によるアルバム『Chuck Person’s Eccojams Vol.1』*2、ヴェイパーウェイヴの原点といわれる)に反応した一群の若い世代の連中、みたいなものだったわけで。彼らはなんというか、『Eccojams』をもとにして……それを様式化した、という。で、僕にとっての『Eccojams』というのは基本的に言えば(中略)「これは、『誰にだってやれる』という意味で、フォーク・ミュージック(民族音楽)みたいなものだ」って。クッフッフッ! 要するに、ゴミの山にどう対処すればいいか、その方法がこれですよ、みたいな(苦笑)」
「そうやってゴミを興味深いものにしよう、と。で、思うにそこだったんだろうね、人びとがとくに興味を惹かれた点というのは。だから、あれは個人的かつキュレーター的な作法で音楽にアプローチする、そのためのひとつのやり方だったっていう」
いま読むと、どこまでも現代川柳のこと言ってるよな、と……。川柳の成立を思うとき、ついいつも選者としての柄井川柳さんのことばかりかんがえてしまうけど、柄井川柳さんに抜かせた句の作者、柄井川柳をして前句付を川柳にさせたひとが、いたんだよな、ということなんかも、ロパティンさんのことばを見てるとかんがえてしまう。
ロパティンさんの言うとおり「誰にだってやれる」音楽だったヴェイパーウェイヴは、模倣もかんたんだった。この真似しやすさも川柳に通じると思う。短さ、題材の取りやすさ(川柳→身の回りの事象風潮+古典教養、ヴェイパーウェイヴ→ウェブ上に落ちている音源)、そして「個人的かつキュレーター的な作法」。だからどちらも一時、爆発的に増えた。
で、ヴェイパーウェイヴはあっという間にフューチャーファンクに解消し、技法のひとつになった。川柳も五七五という形式に収斂し、あらゆるひとの脳内に「五七五のやつ」として定着した。伝統化、と言えるのかもしれない。でももうそこに、未知の鋭さは感じられない。
ヴェイパーウェイヴも川柳も、死んだ。いいえ。普遍のものになって、本体(あえていいます)は潜行しているだけ。
どうして?
そんなの、角が立つくらい逆噴射したいからに決まってんだろ。
かくてここに、両者に共通する媒体特殊性「匿名性」の必然が見えてくる──といったところで今回はここまで。やっぱりなんべんでも聞こう『Chuck Person’s Eccojams Vol.1』からどうぞ。
*1 「OPNはいかにして生まれ、そして新作mOPNへと繫がったのか──ダニエル・ロパティン、インタヴュー(その2)」より(https://www.ele-king.net/interviews/007868/)↩