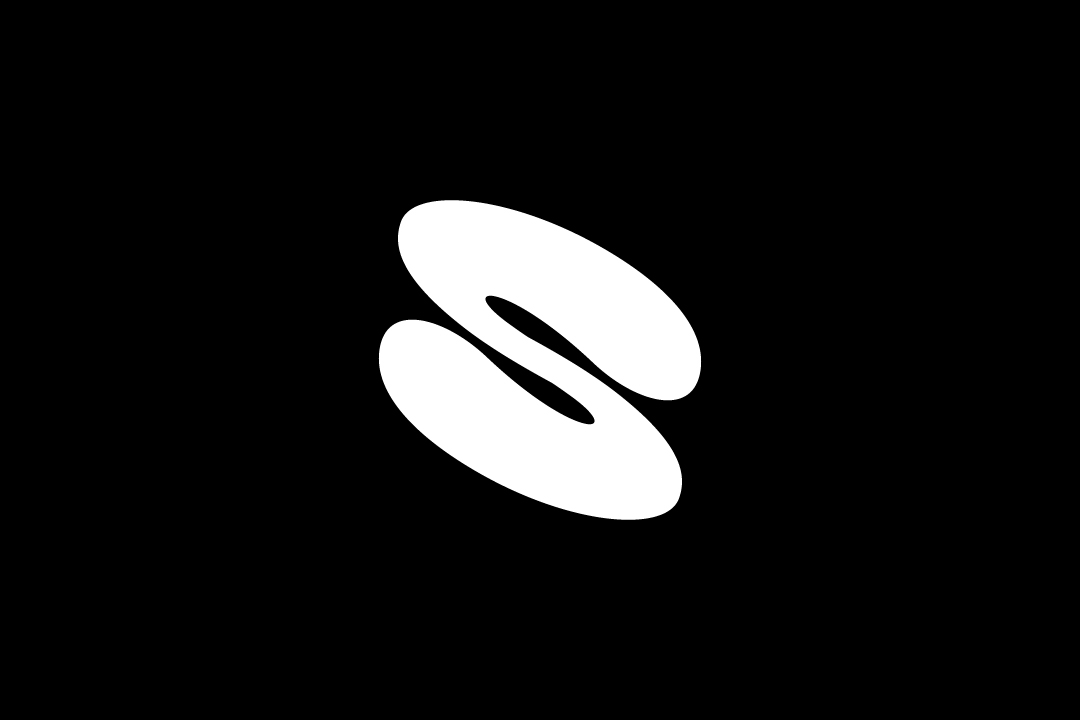一番似合わないのってなんだろうと考えると,おそらく翼だと思う。わたしに翼が生えたら,かなり間抜けで,醜悪なのは違いない。わたしは空を飛ぶようにデザインされていない。一方で,この人は天使みたいな翼を隠してるんだろうな。とかいった印象を見せる人もいる。そういう人を駅や空港で見かけると自分の力だけでどこへでもいけるはずなのにどうして,と思う。それから,背中に生えてる翼の証拠のことはうまく暴けるのに,その人がどんな顔をしていたか,はっきり思い出せない。
2/9 しばらく走っているうちに靴紐が解けた
はじめて車のハンドルを握ったのは,2月の山形の自動車教習所だった。夕闇の時間が過ぎたあとで,視界は真っ暗だった。そして真っ白でもあった。なぜかというと,吹雪が吹きすさんでいたからだ。
すり傷のついたトヨタ・カローラは,数メートルほど進んで,側溝に脱輪した。積雪で,道の白線を見失ったからだ。それが,わたしの一度目の事故だ。
それからは,朝の5時に起きて,ホテルまでやってきた送迎のバスに乗り,カローラを運転し続けた。夜の間に雨が降ると,路面に薄く氷が張りついて,交差点で何度もスリップした。ゆるいS字を描いた峠道を,わずかに残っている轍を頼りに運転した。集落と集落を結ぶ国道は,脅迫的な直線を保っていて,ここではアクセルを思いっきり踏み抜いても,怒られることはなかった。
カローラに乗って2月の国道を走り続けた。お昼の弁当を食べたあと,よくわからない筆記試験をひたすら解かされて,わたしの名前が右上に載った成績表には,わたしの攻撃性の強さに由来した運転適性の懸念点について,3行ほどの説明書きが書き加えられた。それからわたしは新潟で二度目,青森で三度目,最後は自宅の裏の曲がり角で,軽い事故をした。青森では,恐山に登った帰り道だった。その晩,「それってタタリじゃないのぜったいそうだよ」と,わたしの隣に座った女の子は言っていた。
青森での事故は,ぜんぜんタタリによるものとかじゃない。夕方の5時,レンタカーの返却地は,次の信号を左折してすぐだった。気が緩んでた。わたしは半日運転をしたあとで,ハンドルを握る手は疲れていた。軽い痙攣状態になっていた。両目もとっくにしばれていた。後ろからよそ見してるアルファードが突っ込んできてるのがミラー越しにわかってからも,思いきりクラクション鳴らしながら,側道にハンドル切ってたら事故んなかったと思う。でもその時はなんかどうでもよくなっちゃってて,どんどん輪郭がはっきりしてくアルファードをミラー越しにぼんやり見てたら,ばーんぎしぎしと大きな音を立ててぶっ飛ばされた。「衝撃を検知しました。運転手の安全を確認してください」と勝手にナビは喋った。わたしはまったくのところ,安全だった。
運転席から降りてきた男とは,お互いに怪我がないことを確認してから,警察を待つあいだ,楽しい話をした。知らない土地で警察を待つあいだ,男たちは一体どんな会話をするのだろう。楽しい話に決まっている。旅のいきさつについて聞かれ,恐山に行ってきた帰りなんですよ,と答えると,男は一瞬,宙ぶらりんな顔になったが,すぐに柔和な表情に戻った。「ぜんぜん,思ってたのと違いましたよ,あそこ」と,男には言えなかった。それは楽しげな話題ではなさそうだったから。「相撲をやってる息子の全国大会が,十和田であるんです」車から名刺を取って戻ってきた男は言った。ああそうですか,そりゃ,クルマも大きいわけですね。はは,しかし,ぜんぜん来ないですね。お巡りさん。
やがて夜になった。雨が強くなってきた。
8/20 恐山・リアリズム
わたしの先に参道を歩いていた子連れの母親が,石を積んで造られた祠に,赤い風車を挿していた。真夏の正午とはとても思えない冷たい風が,プラスチックで出来た風車をいじめている。風は,湖のほうから流れてくるようだった。道が深く窪んでいるところにガスが溜まっていて,そこを通るとき,硫黄の臭いが目に滲みた。大小様々な祠があちこちに点在している。地獄の底辺を映す水甕に500円玉を投げ入れた。水面は大きく開けた口の形を描いたあと,緑青色をした静けさに戻った。およそ感傷的な気分にはならなかった。冥府の世界を覗き見るには,死の演出が過剰だった。あまりにも現実的な手触りだった。
2/14 わたしが誰を何の目的でガイドしているのかはわからないがガイドにとっての最大の敵は恐らくセンチメンタリズムだと思う。ガイドが感傷的になっていては旅は先へは進めないからだ
山形での免許合宿の終盤になって,雪に閉ざされた世界の往復にいい加減うんざりしていたわたしと,一緒に来ていた友人は,ホテルの近くの居酒屋で日本酒を飲んでいた。塩気の効いたあさりの蒸しものをつまんでいた。朴訥としたマスターが奥から取り出してきた酒は,口に含むと淡い炭酸がはじけながら蜂蜜みたいに濃厚で甘かった。信じられないうまさだった。その知らない酒を何杯も飲んだ。ホテルへ戻る前に少し散歩をしようと友人に提案する。静けさだけが満ちている駅前通り。ゲオがあった。しんとした店内を一周して出る。ゲオの奥にゲームセンターがあった。広い駐車場をわたって入り口の扉を開けた。金髪ジャージの子どもたちとすれ違う。多くの視線にねぶられる。友人とダーツ遊びをした。ぴたぴたに肌に張りついたスウェットを着た高校生たちが,我々を取り囲んだり離れたりしている。それからひとりの女に話しかけられた。3人で何ゲームかダーツをやり,ショットグラスで緑色のお酒を飲んでから,女の運転する車に乗った。
ゲームセンターを出ると,牡丹雪はブリザードに変わっていた。大股で駐車場を歩く女が「どっちが助手席」と振りかえった。迷わず助手席に乗り込む。友人がドアを閉めると,女はレバーをRに入れてアクセルを思いっきり踏み込んだ。ベージュの軽自動車はそのままバックのまま駐車場を一周し,東北中央自動車道へおどり出た。女は2車線の真ん中を走った。120km/hのなか,わざと急ブレーキを踏み,車をぐるぐるに回した。道路は凍結していて,車の回転はしばらく収まらなかった。友人が本当に嫌そうな顔をしたのをミラーで認めて,女は長いあいだ声を出して笑っていた。ハンドルを片手に持ちながら携帯を操作して,プレイリストをシャッフル再生した。スピーカーからとんでもない音量でギターの音が流れる。凍った路面のうえでジミ・ヘンドリクスが唸っていた。
やがて街並みが遠景に退いて,ほんとうに何もなくなった。友人はグロッキーになって,俯いてしまう。カーステレオを止めた女が,静かに道の遠い向こうを見ている。「この道はどこに向かっているの」と聞くと,「山形市」と女が応えた。山形かよ,と呟いた。「東京住んでて免許なんか要るの」と女,うーん,一応あって困ることないし,何歳から乗ってるの車。「14歳」。へえ。
車を動かすのって楽しいよ,合宿楽しんでね。じゃー。と女はホテルまで送ってくれた。新幹線が上野駅に着くまでに,顔とか名前は忘れた。
車のハンドルを握る時間が,日を追って増えてきた。再度ログインするタイムズカーシェア。バックシートにおもちゃの忘れ物,オレンジのサッカーボール。当然だが,自動車の発明は翼を持たない人による。