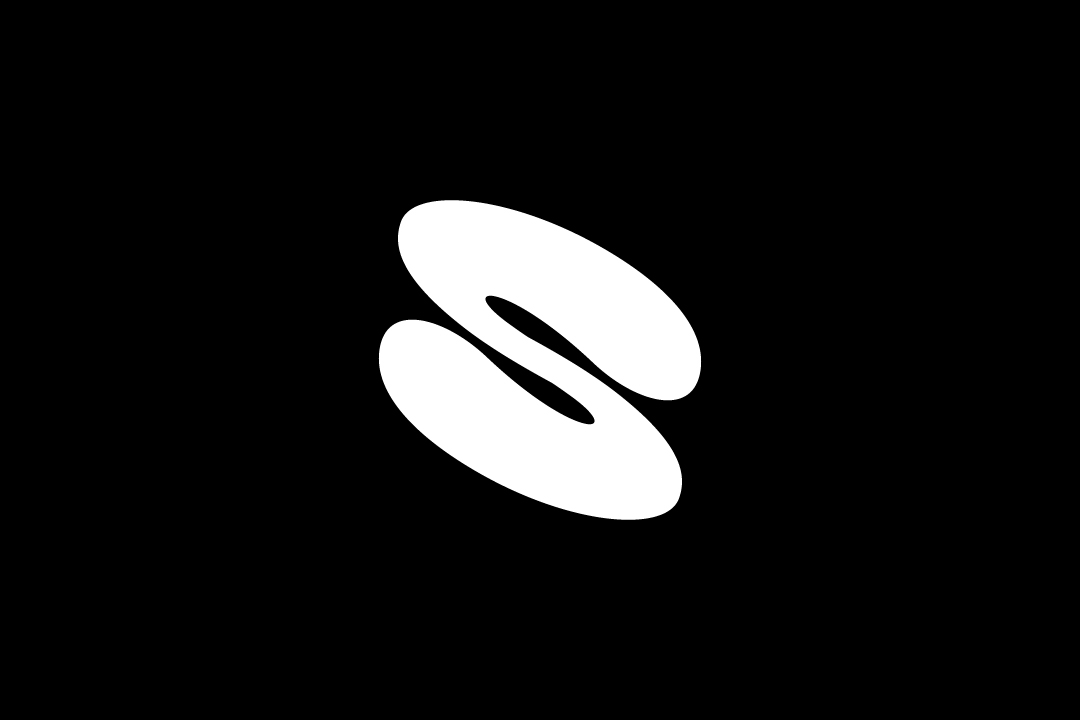¿
教訓
必要以上にもう決して疲れてはいけない、たとえおまえの骨の疲労に基づいて文化を築くにせよ。
──アントナン・アルトー「此処に眠る」
快楽主義などで有名な古代ギリシアのエピクロスの死についての考えをはじめて知ったのは、私が小学六年生の頃だったと思う。小さいころは、死ぬことがすっごく怖かった。どうだろう? 「死」ってなんなんだ。ビッグ・クエスチョンを別に忘れて過ごさなくてもいい。
私が見聞きしたものは、死についての論証ではなく、結論だけだ。それは、なかば箴言めいたものだった。
エピクロス曰く、死は我々にとっては何ものでもない、なぜならば、我々が現に生きている間は、死は我々のところにはなく、実際に死がやってきたとき、われわれはもはや存在しないからである。これ、どこかで聞いたことがあるだろう? かくして、子どもの俺にとって死はなにものでもなくなる。やや厳密に言えば、私の死が。私が死ぬことを恐れる必要はないのだ。なぜならば、生きている間に死はやってこないのだから……。
エピクロスのこの箴言には、高校生のときにもう一回、公民の参考書かなにかで出会った。そのときもまた感銘をうけた。けれども、高校生の私は小さい頃と違っていた。死ぬことが怖いのは変わらないのだが、さらに、私は(……あなたは?)、死にたかった。私の死に対する恐怖と、現に私があることによる悲しみとが混ざっていた。だが、エピクロスの箴言を盲目的に納得し続ける必要があった、というかむしろ反駁する手札をもたずにあった。死が私には属さずにあるような集合のベン図の表象が持続していた。だが、これは決して健康ではないはずだ。
¿
自死への欲望とは、大抵、自己実現の欲求から生じる。何事かを成し遂げるまではいかずとも、少なくとも死はこの状況を一変させるに違いない。強く生きようとする人間ほど、それだけ自殺するだろう、とペシミズムの彼は言った……。こうした手短な、自死を最高の自由の行使とみなす傾向についての分析は、ショウペンハウワーとその注釈者らに任せることにしよう。
私が現にあるこのさしあたりの世界がまるっきり変わってほしいわけではない。私はむしろ、現に世界がありつつ、現に私が生きてありつづけて、なおも死に、そしてなおも生きたいのだ。小学生の私も、高校生の私も、今の私も、これからの私も。〈自死〉とは、むしろ変身なのだ。
私が変身したのだとしたら、私は死を経験している。私が死を経験しているのだとしたら、私は死を経験しなおすことができるかもしれない。私は、変身したいと望むときには、自死できるように私を構成するかもしれない。ただし、メランコリーからではなく……、脳を損傷するわけでもなく……、ニヒリズムに支配されてでもなく……。
¿
ここで書かれる自死ないし自殺の話は、「こころの健康相談統一ダイヤル」でも「いのちSOS」でもないし、各宗教における死の問題でもなければ、『ケンブリッジ大学・人気哲学者の「不死」の講義』でもない。私と一緒に、自死とは何なのかを考えよう。私とは何者で、私でないものとは何者なのかを考えよう。死とは何なのかを考えよう。子どものように……。倫理を考えよう。酔っ払いのように……。
ここで言われる自死とは何か。自殺と呼んでもかまわない。〈自死〉にせよ、〈自殺〉にせよ、変身に──すなわち〈別の身体へ〉の変形に──配慮して、この現象を括弧に入れることにしよう。自死とは、絶対にありえないものである。スピノザは、こう言表した。
「だれも自己の本性の必然性から食物を忌避したり自殺したりはしない。外部の原因に強いられてそうするのである」(『エチカ』 第4部定理20備考)
私たちは、自殺できない。
私は、スピノザのこの言表は正しいと解する。今日まで言われてきた自殺とは、決して自己原因から生じたのではなく、外部原因から生じたものなのだ。
「物はできる限りそれ自身としてあり続けようと努める努力を持ち、この努力が物の本質である」(第3部定理6-7)
スピノザが問題提起した努力を信じよう。
ただ、いかなる物も自己の存在を維持しようとする努力を有するにも関わらず、なぜ自殺が存在するのか。こうして、スピノザにおいては、フロイトが快原則の彼岸で打ち出した死の欲動というあの大胆な仮説は認められなくなる1。フロイトはおそらくやや戸惑いながら言った、すべての生命の目的は死である……。
スピノザの自殺の否定の言表には続きがある。
「隠れた外部の諸原因が、その人の表象作用をある態勢に置いて身体を変状させ、その結果身体が以前の本性に反する別の本性[…]を帯び、その人はみずからを殺害する、というふうに[自殺する]」(第4部定理20備考)
なるほど。私たちは、それが外部の原因であるにも関わらず、自己原因だと勘違いすることで、自殺がありうるのだ、と。死の扱いには固有の多くの問題がある。例えば、この社会において現に生じている事実をどう扱うのか、というツッコミがあるだろう(……なぜ自殺が存在するのか)。
「身体が何をなしうるかをこれまで誰も規定しえなかった」(第3部定理2備考)
後のフロイトを先駆者にして、精神分析の名のもとで有名になる〈無意識〉は、かくして人間が身体を有することに由来する、とスピノザならば言うだろう。精神は、身体が何をなしうるか知らないのである。ここに、フロイトが大胆に提示した死の欲動が、スピノザの『エチカ』と幾度となく比較される理由がある。
¿
変身というよりも、むしろ異装の思想家ジュディス・バトラーは、スピノザのこの勘違いの問題に接近する。バトラーにとっては、私たちの自殺を原理的に不可能にさせる努力の規定は不満である。バトラーが配慮するのは、社会的な承認のプロセスから排除されてしまった人間が自死を迎えた場合、それはやはり「外的原因」によるものである、と片付けてしまうことができるだろうか。という問題である。藤高は『ジュディス・バトラー:生と哲学を賭けた闘い』において、バトラーの思想を要約する調子で述べる。
果たして自殺が本当に「外的原因」によるものであり、それはコナトゥスと内的に関わらないものなのか[…]ある種の自殺には「生」への、「承認」への欲望が賭けられているということはできないだろうか。アントナン・アルトーがヴァン・ゴッホを「社会が自殺させた者」と呼んだように、その生は別の社会的世界では可能であり、その死は別の、そこでなら生きることが可能であるような社会的世界を希求するものとして考えることはできないだろうか2。(強調ササキリ)
藤高=バトラーが賭けるのは、自殺につながる勘違いが生じないような別の社会があったかもしれない、その可能性ということだ。
とはいえ、バトラーのようなアクロバティックなコナトゥスの読み直しがなくとも、スピノザは「新しい身体の存在論」3からそれほど遠くない位置にいてくれている、ように思われる。
バトラーに限ったことではないが、一般に、「社会」という語は、自己と無数の他者からの承認プロセスを表すような広い意味と、自己とより少ない他者との触発関係を表すような狭い意味での語とが、それほど明確に分けられていないように思える。一方に広い社会……、擬人化され超越化された神、人間的な意味と価値付けによってヒエラルキー化した世界、ニヒリズムの様態たる人間の巨大な三角回路、他方に狭い「社会」……、自然と、外部の物と、自己とからなる最小の三角回路……4。
¿
『問題=物質となる身体:「セックス」の言説的境界について』の著者ジュディス・バトラー曰く、セックスとは、それ自体としてあるものではなく、社会的規範によって強制的に規定され、管理され、生産されるようなものである。鮮烈な指摘である。生物学的な性とは、事実として存在するわけではない。おそらくこれは、ある事例の研究としてほとんど正しいだろう。
フロイトは「喪とメランコリー」において、無意識的なメランコリーにおいて自己は、愛する他者を喪った場合に、その対象が何であったのかを知らないのだ、と言った。すると、愛する他者を知っているような喪(悲哀)の働きとは、すなわち誰を失くしてしまったのかを知っているような場合における働きとは異なり、自己は、その愛する対象に自己を同一化させることによって、その喪失を解消しようとする。自己が愛する対象そのものになるのである。悲哀において、愛する他者に対して「ああ、なぜ私をおいていなくなってしまったの!」と責める相手が、メランコリーにおいては不在であるため、自分を責める。
こうしたシンプルなメランコリーの理論の異性愛性を暴きながら、変形したメランコリーの援用を、バトラーは至るところで行う。「話すこととは、常に何らかの意味で、自分自身を通じて、自分自身として他者が話すことであり、決して自分が選択したのではない言語、自分が使うべき道具として見出すことのない言語、言わば、それによって使われ、その中で所有権を奪される言語を、「自分」や「私たち」の不安定で継続的な条件、拘束する権力の両義的な条件として、メランコリー的に反覆することなのだから」5。
たしかに私の身体を介したメランコリー的変形=異装によってある種の主体のずらしが達成可能なのかもしれない。異性愛主義のこの世においては同性愛が予めの排除された状態である。排除されたものは、喪に服することができず、メランコリーに陥るしかない。というかむしろ、メランコリーによって、この愛する対象である同性愛を保存する。かくして、異装は複雑な仕方で異性愛の規範を暴く……。
¿
例えば、バトラーの社会・道徳・倫理の混乱をよく表す記述がある。バトラーは、道徳の起源を見事に説明したニーチェの『道徳の系譜』に翻弄されている。「ニーチェ[の『道徳の系譜』]は「疚しい良心の始まり」を、「暴力によって潜在的なものとされた自由への本能」と記述している。[…]それが見出されるのは、苦痛を加える際に得られる快の中、道徳性のために、道徳性の名の下で自分自身に苦痛を加える際に得られる快の中である。従って、以前は債権者に帰されたこの苦痛を与える快楽は、社会契約の圧力の下で、内化された快に、自分自身を迫害する悦びに変わるのである」6。
『権力の心的な生』において、ニーチェのこの「処罰の光景」を一旦は受け入れる。バトラーはこの時点では、ニーチェが説明する道徳を内側に取り込み、自らを迫害することのこの愉悦を、主体化の過程の必須項目だとみなすのである。他者から苦痛を与えられる構造の不快から快に転換するようなこの構造は、次々と変奏されうる。例えば、オイディプス的な関係……、例えば、一人では生きることができない幼児が、親に服従することにより、むしろその生の安全性を得るような関係……、等々。ニーチェはとりわけ『道徳の系譜』において、いかにしてこうした疚しい良心が形成されていったのかを見事に説明したのみであって、決してそれが主体の第一義的なものであるとは述べていないだろう、と私は考える(『道徳の系譜』における疚しい良心は確かにある種のアンビバレンスがあるものの、基本的には、この良心批判である)。
『権力の心的な生』を書いた1997年のバトラーは、以降、とりわけ2005年の『自分自身を説明すること』において、こうしたニーチェの疾しい良心の説明における処罰の光景を倫理において取り入れかけたことを自己批判する。
「『権力の心的な生』において、私は主体を創始するこの処罰の光景をあまりにも性急に受け容れてしまったかもしれない。この見方によれば、処罰制度によって私は私の行為に結びつけられるのであり、また、私があれこれの行為をしたという理由で処罰されるとき、私は意識の主体として、従ってある意味で、自分自身を反省する主体として現れる。主体形成に関するこの見解は、法を内面化した主体という見方に、あるいは少なくとも、処罰制度が償いを求めるような行為へと主体を因果的に関係づける見方に依拠している7。」
バトラーは、主体化の過程を説明するにあたって、ニーチェの処罰の光景を受け容れたことのデメリットを並べている。法を内面化する。こうした法の内面化と悪の問題のカント的な議論については今のところは立ち入らないようにしよう。
バトラーは、カフカの『判決』(ほんの一言で結末を説明すると、主人公ゲオルグが父親に自殺を命じられて自殺をする小説である)を読みながら、まさにスピノザの自殺論に抗って反省する。
「もしスピノザが言うように、人は既にあるいは同時に生への欲望を持つときにのみ正しく生きる欲望を持つのだとすれば、生への欲望を死への欲望に変えようとする処罰のシナリオは倫理の条件そのものを侵食する、ということもまた正しいように思われる8。」(強調ササキリ)
こうしたバトラーの混乱の一つの過程は、ニーチェが倫理的な主体化と想定していたものではない道徳的な主体化を、倫理にあてはめようとすることから生じたように思われる。新しい身体の存在論。おそらく、バトラーは、人間の古い身体の存在論をほとんど考慮していない。たしかに、こうしたあてはめの戦略は、アイデンティティを撹乱する場合には極めて有効であるだろう。なぜならば、権力による法システムが主体を形成するのであれば、むしろその法システムを引用ないし反復することによって、この主体の位置をずらすことが可能だからである。
ただし、それがやはり死に向かわない限りにおいて、という節約がなければならない。こうした引用ないし反復もできないような、絶対的に死に向かうような命令がある場合に、攪乱の戦略は頓挫せざるを得ない。ゲオルグが受けた自殺の〈判決〉。
広い意味で社会という語を扱うと、すなわち道徳と倫理とを混同すると、仮にバトラーに倫理的転回が起こったのだとしても、スピノザの努力は変形されなければ、受け容れきれなくなる。
たしかに、バトラーは身体の物質性の思考を極限まで推し進めただろう。だがこのような場合に、見過ごされているスピノザの古い、反時代的な身体の存在論がある。倫理の条件を見失ったのは、決してニーチェのせいではないはずだ。
自分の言葉を反復しよう。……さらに、私は(……あなたは?)、死にたかった。
〈別の社会へ〉の戦略は、確かに実践的であるのだが、死の前では、きっと努力を無理に変形せざるをえない。私の愛が、反対に憎悪へ転換してしまうような現象を自然に考えることができないのだ。努力とは自己の本質であり、自己は、自己が存在を持続するように努める。すなわち、努力は、自己の存在への根源的な愛なのだ。フロイトが言うような、愛に対応したエロスと、憎悪に対応したタナトスがあるわけではないだろう。このような愛と憎悪を対立させるフロイト的な思考は、いかにして憎悪を、その極である死の欲動を、愛に、すなわち生に転換しうるのかの理解が困難になるだろう。
¿
人間身体がその本性とまったく異なる他の本性に変化しうることが不可能でないと私は信じる。なぜなら、人間身体は死体に変化する場合に限って死んだのだと認めなければならないいかなる理由もないからである。かえって経験そのものは反対のことを教えるように見える。というのは、人間がほとんど同一人物であると言えないほどの大きな変化を受けることがしばしば起こるからである。(第4部定理39備考)
スピノザは、〈死体〉と死を明確に分けてしまった。ここでは、驚くべき〈身体の死〉が構想されている。死体にならず、身体が死ぬような例をスピノザは2つ挙げている。一つは、病に襲われ、記憶喪失をして、母語まで忘れ、大人の姿をした赤ん坊のようになってしまった詩人。もう一つは、まだ口のきけない赤ん坊が大人に成長すること。
この一つ目の記憶喪失の詩人に力点を置き、ある種の変身を描き出そうとしたのがマラブーである。マラブーの『新たなる傷つきし者』ではたった一度、この死体と死の区別がなされる第4部定理39備考が引用される。後の著作『偶発事の存在論』でスピノザがより詳しく論じられることになる。
人間が、死体になるまえに死を経験してしまうようなことがありうる。同じ人間だと同定することが難しいくらいに。それまでの人間と同定できなくなるほど、破壊的変化をこうむることがありうる。破壊的可塑性がある。「情動的冷淡さとして、脳のなかに死の欲動が刻印されているということは、脳損傷者、統合失調症者、連続殺人犯、心的外傷経験者、その他の排除されし者にだけ見られるのではなく、潜在的には、私たちの一人ひとりの内に脅威として存在するのである。現代の神経生物学の言説は、おそらく、『人は身体が何をなしうるかを知らない』というスピノザの言葉を、より根源的な形で媒介することになるだろう」9。マラブーは書く。マラブーが推し進めるのは、徹底的に〈脳〉の問題である。
フロイトの死の欲動は、こうした情動的冷淡さに、脳の問題にずらされている。マラブーは、まだ口のきけない赤ん坊が大人に成長するという死の二つ目の例を、子どもから大人への変化というよりは、ある種の老いの問題として捉える傾向にある。
例えば、アルツハイマー病は「新たなる傷つきし者」に含まれるだろう。マラブーからこうした冷淡な変身の可能性が提示されるのは、一方でこのように具体的な症例であり、他方で文学の読解(例えばカフカの『変身』・プルースト)からである。むしろ後者の文学のほうに軸を移したい気持ちになるのは、何も私は脳を損傷するように今すぐに私を再構成したいわけではないからである。「彼[フーコー]はベケットの次の言葉に注意をうながす。『誰が話そうとかまわないではないか、誰かが話したのだ、誰が話そうとかまわないではないか』[…]エクリチュールの主体の無関心は、苦しむ主体ないし外傷をこうむった主体が、快原則の彼岸に去ってしまおうとすることを示す、あの無関心から、それほど遠いものだろうか」10。
あくまでささやかな示唆に留まるが、マラブーは脳損傷による変身の問いを、エクリチュールの問い、書かれた言葉に誰が署名したのかという問いとを結び付けようとする。言葉によるわれわれの中途半端な変身……。
¿
われわれは、この生において何よりも幼児期の身体を──その本性が許容し促してくれる限り──きわめて多くのことに適した別の身体へ変化させようと努める。すなわち、きわめて多くのことに有能な身体、そして自己と神[=自然]と物とについてもっとも多くを意識するような精神に関係する身体に変化させようと努める。(第5部定理39備考)
〈別の身体へ〉の生成変化。実のところ、スピノザはこの別の身体が何であるかをほとんど語っていない。だが、これだけはわかる。先に述べた、狭い「社会」……、自然と、外部の物と、自己とからなる最小の三角回路を、より多く意識するような身体への変化を志向していることは。ニーチェが述べたような、ニヒリズムが蔓延し、自己を叱責することを快とするような疚しい良心が台頭するような社会ではない、狭い社会を。
スピノザにおいて、身体と精神は全く存在論的に等価である。精神は、まずもって諸観念の集合体であり、観念は、何かについての観念であり、観念の対象は、身体しかない。ただし、精神は、自己の身体そのものを知覚できず、自己の身体の変状を知覚する。自己の身体の変状。自己触発(自己自身が原因の刺激)か、あるいは異他触発(他者が原因の刺激)か。
このように、人間の精神は、自己の身体の無数の触発それぞれに対応した無数の観念からなる。かくして、〈身体の変状〉と、〈身体の変状の観念〉とから私たちができている、というスピノザの有名な心身並行論と言われるものができあがる。スピノザは精神に決して特権的な地位を与えたりしない。これは古い、反時代的な身体の存在論である。
さて、ここから感情を考えることができる。スピノザは基本感情として3つを定義している。喜びと悲しみ、および、欲望。欲望とは、先に述べた努力のことである。喜び/悲しみの対にいこう。これらは、いままで出てきたことから以下のように理解できる。
外部のある原因によって、身体が変状し、身体の活動力能(かつどうりょくのう)が増大する場合は、精神の思考力能は喜びを感じ、逆の場合は悲しみを感じる。こうした感情は基本的に受動的なものである。喜びの派生感情として愛が理解され、悲しみの派生感情として憎悪が理解される。すなわち、愛とは、喜びと外部の物体の観念とから成り、憎しみとは、悲しみと外部の物体の観念とから成る。努力はむしろ、喜びと手を取り合って至福へと向かう思想として理解されてきた。
¿
だが、スピノザは、人間には、まったく憎悪を向けられる理由がないにも関わらず、憎悪が優位となるような場合には、愛する対象に害を与えるような残酷と呼ばれる感情がある、と述べている(第3部定理41、系、備考)。
憎悪を向けられる理由、怒りも復讐心もなしに、ただ、悲しみと、外部の物体の観念である愛する対象とから成る絶対的な、能動的な憎悪がある。この特異な憎悪は、残酷と呼ばれる。ニヒリズムの徹底ではなく、こうしたニヒリズムそのものの破壊を企てるスピノザ主義者である江川は、この残酷を能動的憎悪と解する独特の解釈、アルトーとスピノザの〈残酷〉と〈別の身体〉とを繋ぎ止める解釈を、その全ての著作、とりわけ『残酷と無能力』にて繰り広げている。
この能動性を、レヴィナスの有名な、受動性よりももっと受動的な受動性を響かせながら。「私が命を絶つとすれば、それは自分を破壊するためではなく、自分を再構成するためである。自殺とは私にとって、力ずくで自分を取り戻し、自分の存在に容赦なく闖入して、神のあてにならない前進を追い越すための一つの手段であろう」(アントナン・アルトー「自殺について」)。江川はこのアルトーの自殺の考えをスピノザを介して以下のように理解する。
「自殺は、自己破壊ではなく、自己の再構成である。自殺のあるところには、むしろ人間の再構成がなければならないのだ。死体になる前に死を迎えるということ、それは、自己再生であり、身体の一つの不死である。思考の無能力は身体の最大の力能につながっているのである11」
自己の再構成とは、まず自己の本質を憎悪することから開始される。この場合、努力は自己の本質に対する愛と憎悪とに同時に襲われ、憎悪が優位となるならば、すなわちまったくの無力能となるならば、自己の本質を変形してしまうだろう……。
このように、努力から出発してもなお、……私は(……あなたは?)、死にたかった、ことがありうるということになる。というかむしろそれは、人間の本質を変形する、別の身体への変身であったということになる。変身したいと望むときには、自死できるように私を構成するだろう、と私は言った。これには微妙な間違いがあった。能動的な憎悪がどうやら存在し、この残酷が進むと、私は必然的に自死し、私は再構成されるだろう。私の愛が、反対に憎悪へ転換してしまうような現象が少なくともあるだろうということは、スピノザの喜び/悲しみの比例関係において明らかになっただろうし、また絶対的な悲しみが持つ価値が少し見えたように思える。死の観念を曲げて、再構成する。だが、「私」や「憎悪」ってなんなんだ。それらの観念は、まだそれほど曲がっていない。
脚 注
- 例えば、イルミヤフ・ヨベル『スピノザ 異端の系譜』(小岸昭ら訳、1998、人文書院)のとりわけ「第六章 スピノザとフロイト―解放としての自己認識:フロイトと科学」を参照されたい。ほかにも、最近出版された川谷大治『スピノザの精神分析:『エチカ』からみたボーダーラインの精神療法』(2024、遠見書房)等では、より(精神医学的な意味での)臨床的な議論が行われている。 ↩︎
- 藤高和輝『ジュディス・バトラー:生と哲学を賭けた闘い』(2018、以文社、p.30) ↩︎
- a new bodily ontology。バトラー『戦争の枠組:生はいつ嘆きうるものであるのか』(清水晶子訳、2012、筑摩書房)での、自身の思想の呼ばれ方。大貫挙学「ジュディス・バトラーにおける「身体」の「政治性」」(2024、佛大社会学、48; 30-40. https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/BS/0048/BS00480L030.pdf)に詳しい。 ↩︎
- 例えば、江川隆男『すべてはつねに別のものである:〈身体─戦争機械〉論』(2019、河出書房新社)所収の「破壊目的あるいは減算中継:能動的ニヒリズム宣言について」や「最小の三角回路について:哲学あるいは革命」を参照。あるいは、江川隆男『スピノザ『エチカ』講義:批判と創造の思考のために』(2019、法政大学出版局、pp.209-211)を参照されたい。
また、スピノザの『エチカ』は以下の備考で終わる。
以上をもって私は、感情に対する精神の力能ならびに精神の自由について示そうと考えていた一切を終えた。そこから、知者はどれほどのことができ、欲心にのみ駆られる無知な者よりどれほど有能であるかが明白となる。じっさい無知な者は多くの仕方で外部の諸原因から追い立てられ、真の心の満足を一度たりとも得ることがない。のみならず自己と神と事物をいわば意識せずに生き、受動することをやめると同時に、あることをもやめる。反対に知者は、知者として見られるその限りでほとんど心を乱されることがなく、自己と神と事物をある種永遠の必然性において意識しているので、あることを決してやめず、常に真の心の満足を得ている。こうしたことへ導くものとして私が示した道はいまは険しく見えるかもしれないが、それでも見つけることはできる。たしかに、こんなにも稀にしか見いだされないものが峻険でないはずはない。なぜなら、救いがすぐ手近にあって大した労苦なしに見いだされるのだったら、どうしてそれがほぼ万人に顧みられないままでいられただろう。だがすべて高貴なものは、稀であるとともに難しいのである。(第5部定理42備考)
ここで言われている「知者」を狭い社会の人間、「無知な者」を広い社会の人間と読んでみるといかがだろうか。この後で、私はバトラーの攪乱における主体を「無知な者」に属すると言いたいわけではない、という微妙さに留意されたい。この微妙さを人類が語るには、まだ別のリズムが必要であるように思われる。 ↩︎ - ジュディス・バトラー『問題=物質となる身体:「セックス」の言説的境界について』(佐藤嘉幸監訳、2021、以文社、p.331)。最後の一文である。 ↩︎
- ジュディス・バトラー『改訳決定版 権力の心的な生:主体化=服従化に関する諸理論』(佐藤嘉幸・清水知子訳、2012、月曜社、p.94) ↩︎
- ジュディス・バトラー『新版 自分自身を説明すること:倫理的暴力の批判』(佐藤嘉幸・清水知子訳、2024、月曜社、p.25) ↩︎
- ジュディス・バトラー『新版 自分自身を説明すること:倫理的暴力の批判』(佐藤嘉幸・清水知子訳、2024、月曜社、p.73) ↩︎
- カトリーヌ・マラブー『偶発事の存在論:破壊的可塑性についての試論』(鈴木智之訳、2020、法政大学出版局、p.70) ↩︎
- カトリーヌ・マラブー『新たなる傷つきし者:フロイトから神経学へ 現代の心的外傷を考える』(平野徹訳、2016、河出書房新社、pp.305-306) ↩︎
- 江川隆男『残酷と無能力』(2021、月曜社、p.46) ↩︎