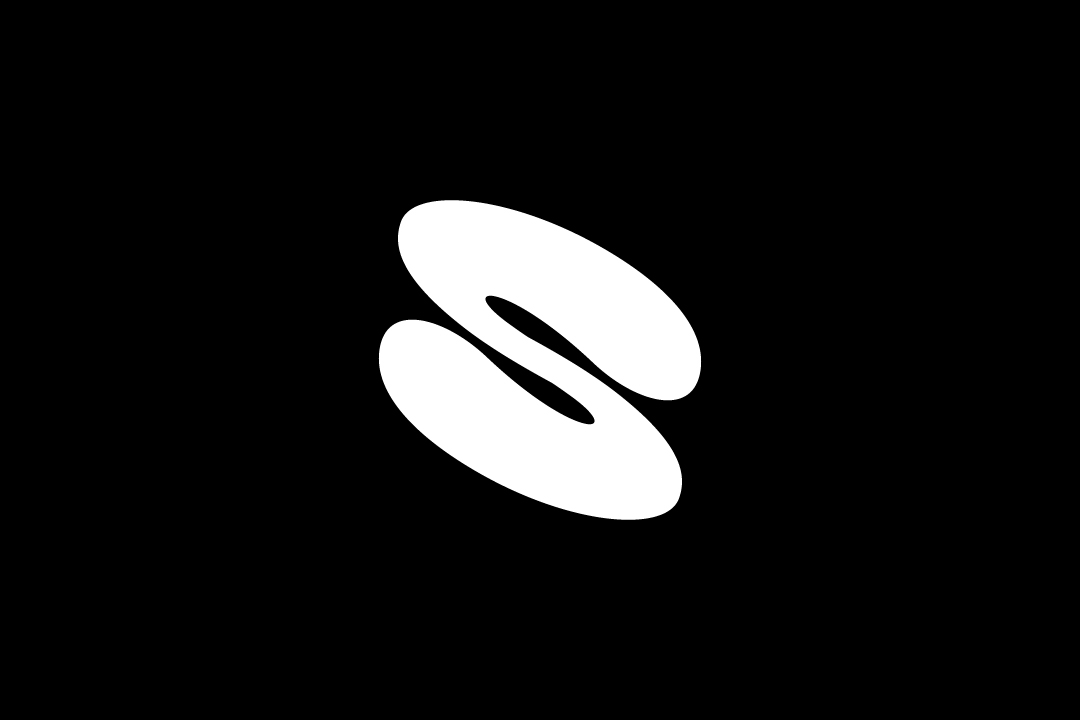¿
俳優は途方もなく執拗な努力をしなければならず、
それらの努力は時間においては何時間も、ほとんど丸一日になるまで続けられるかもしれない
そしてまた彼には必要なのだ、
そこに達するためには、
法外であるとともに単純な、
異例であるとともに法外な演技の仕方が。
疲れ果てた俳優の身体には、現代の医学にはもはやその知識はないが何冊かの古い錬金術の書には逐一記述が見出せる、特殊な治療法の基礎原理が必要だ。
─アントナン・アルトー「ピエール画廊で読まれるために書かれた三つのテキスト」1
¿
前回の記事では、「死」の観念を曲げる準備をすると言った。「死」を曲げるには、「私」と「憎悪」も曲げる必要があるとわかったので、あくまで準備だった。自死を身近なものにするために、私は極まった中途半端さを書き記して、私やあなたの不死を言祝ごう。私は私を追い込むかもしれないし。私は白痴かもしれない。でも俺は、そうした征服に逆らって、治療法の基礎原理を記述しよう。
エピクロスは、死への恐怖なんて、死は生にとって何ものでもないんだから大丈夫だと言った。だが、私は、死を先取りして、死への恐怖を感じ、また死への恐怖を治療すること……。これを為しうるのだ。と反論しよう。
¿
自己への愛の消尽の結果としての〈自殺〉。自己の本質としての努力なる自己への愛と、これとは見かけ上は反した憎悪とに同時に襲われ、憎悪が優位となるならば、自己の身体を排除する方向にはたらくだろう、そして、自己の本質を変形してしまうだろう……。こうした〈残酷〉は能動的な憎悪である。スピノザの『エチカ』から導かれた、こうした残酷を経ることで、或る身体は別の身体へ変身する。欲望の特異な派生感情としての残酷とは、憎い対象に向ける憎悪ではなく、愛しい対象に向ける憎悪なのだ。
残酷における能動的憎悪の前景化は、アルトーの中にあった。と人は言うだろう。何故ならば、残酷とは、〈別の身体へ〉変身することであり、アルトーがこの〈別の身体へ〉の欲望を確かにその作品のなかで何度も言表したからだ。だがまだ、彼、アルトーの中にあったというだけで、どのように私の愛が反対の憎悪に転換してしまうのかについては、実際のところ明らかになっていない。「それにしても、ただアルトーだけが……2」、「誰がこの身体を信じることができたのか。誰が因果性とはまったく無関係な身体の感覚に意識が穿たれたのか。アルトーだけではないのか3」ただ一人、英雄アルトーの身体にだけ残酷が上演されたのか。「しかし、私はアルトーを少し概念化しすぎたのではないかと畏れる4」と江川は言った5。
ここで私が考えたいのは、以下のような問いである。この私に、残酷=能動的憎悪が生じるのか? するとしたら、どのようなはたらきで?
私は、置いてけぼりにされている。ただアルトーだけが変身可能で、それ以外は変身不可能なのだという感覚が現にある。アルトーを教義化したいわけではない、というエクスキューズだけで払い除けられるものではないはずだ。彼だけが、自殺を免れつつも〈自殺〉をし、私が(あなたが?)ただバトラーが言うような勘違いのもとで自殺するとしたら……。バトラーの自殺は一般に正しい。アルトーは自殺していないし、〈自殺〉はしている。のもまた正しい。
死への恐怖は、驚きと、復讐心や怒りとが混じって形成される、道徳的な感情である。そうであるとして、恐怖でない仕方で私はいかにして道徳から倫理の次元に移行しようか。他人からの自殺せよとの命令を受け取り、取り込み、自殺したゲオルグ(カフカ『審判』)。法に対する服従化を内面に築くことは、自殺の問題をぼやけた道徳的なものにしてしまう。スピノザは残酷なる欲望による変身を示唆した。アルトーはそうした。アルトーは開示したのだ。アルトーの英雄化──つまりアルトーの教義化──と、アルトーの奪還との間を揺れ動く中途半端さは、憎悪をよりよく描写することからはじめることができると考えたい。注意されたい。残酷さは、スプラッタ映画のようなものではない。
さて、喜びには決して転じないような、絶対的悲しみとしての能動的憎悪は、他者不在の世界に生じる。
なぜか。普通、事物は、その事物以外の他の事物である多くの他者からなる世界にあり、他者から触発を受けることによって、喜びや悲しみを感じている。能動的憎悪においては、喜びや悲しみの原因となる、この身体の活動力能を増大ないし減少させるような可能性が消尽しているからである(こうした証明は全て江川に負っている)。他の事物が存在するならば、その事物が自己に喜びを与える可能性がまだあるはずだ。だが、絶対的な悲しみがありえるとしたら、もはや他の事物はないのである。他の事物とは、喜び/悲しみのが生じる原因、その勝機なのだ。他の事物の存在は、千にひとつか、万にひとつか、億か、兆か、それとも京か……。それでも那由多の彼方には充分に喜びの可能性がある。
だから、能動的憎悪=残酷においては、絶対的孤独に陥る。すると、能動的憎悪において、むしろ自己の身体の本質しか残らないのである。このことは、この後に生じる私の再構成を予報するのだが、むしろいま強調されるべきことは、こうした他者不在の絶対的な孤独においても、この私はやはり現にあり、私はこの孤独な条件のなかで憎悪が可能であるということだ。むしろ、能動的憎悪の条件とは絶対に孤独であることだ。本文では、「孤独」の観念がもっとも曲げられることになる。
¿
結局のところ、死の観念を曲げる準備のためには、私がどのように構成され、私でない他者がどのように私と分けられるのかを考えなければならない。さもなければ、私がこの私であると言うこと、貴方は私とは異なる他人であると言うことができなくなるからだ。「[プラトンが書いたソクラテスと対話したエレア派の哲学者]『パルメニデス』のまねをして、そしてこれ以上思弁の森の中に足を踏み入れずにこう言おう。──それ自身とは他なる言述のみが、他者性のメタ・カテゴリーには適しているのである、さもないと他者性はそれ自身と同じになって自殺してしまい……6」パルメニデスの説得的な、ソフィスト的な自殺。「他」も「自」も等しいとは言わないさ……。
デカルトが、私は思う、故に、私は在ると最初からはいわずにおいて、私は在る、私は実存する。と言ったにせよ、あるいは続けて、欺く神が欺くなら、私は在る、と言ったにせよ。私は思考する、私はある。と言ったにせよ、このときから〈私〉の地価はあるときには野垂れ死んでもおかしくないほどに暴落し、あるときは豪遊し放題なほど極端なまでに高騰してきた。
おそらく、この「私」の地位が最も失墜したときは、レヴィナスが『存在するとは別の仕方で』を書いたときである。
レヴィナスにとって「私」は、「どんな受動性よりも受動的な受動性[…]は、出血さながら自己を枯渇させる可傷性7」によって、自分がたとえ死に瀕しつつも、他人のために、というか他人の身代わり8になって、いかなる迫害も、いかなる非難も、いかなる悪も引き受ける。私がいかに腹を空かせてようが、他者はすでにもう腹を空かせている。私は他者に、応答する責任(responsibility=責任=答えることができる……)において、最後の一つのパンを渡す。私は食物を忌避する……。「〈他者〉に接近する際、私はいつも「約束」の時間に遅れている9」のである。「他者に対する責任──、[…]もはや測ることのできないこの無制限な責任は、代替不能な人質としての主体性[≒身代わり]を要請し、迫害の受動性のうちで、[…]主体性を剥き出しにしてゆく。〈自己〉のうちへ、存在することの外へ──、死に至る受動性なのだ!10」(強調ササキリ)。かくして、レヴィナスは、誇張11的に私の地位を奪う。「私」は初っ端から、他者に対して無限の、取り返しのつかない責任がある! 存在しはじめた途端に、私は返しきれない負債を負っている。確かに私は成立するのだが、それは他者なるものの現れの対格においてでしかない。
故に、レヴィナスにおいては、実のところ部分的には「私」は孤独ではない。
I’ll leave you two alone.
ここでレヴィナスが上昇させる憎悪の言語は、一見したところスピノザ=アルトーの残酷からそれほど距離がないように思われるが(これ自体は極めて魅力的である)、しかし、レヴィナス本人は、自らのこの思想の古さの位置付けを強調する。この迫害される主体は、現働的本質というエゴイズムの手前にある、と。ああ、古いレヴィナスよ、……この息切れ……、だが、必要以上に疲れてはいけないのではなかったか。
レヴィナスには、疲れ果てた身体を治療する記述が欠けているだろうし、調査官が用意されなければならないと思われる。
さもないと、憎悪を愛に反転させることができないどころか、むしろ私の存在そのものも、私の家を、文化を築く枠も、むろん肉も、血も、灰すら残らないほどに焼き尽くされてしまうだろうから。
¿
レヴィナスは、「私」をいけるところまで下降させてみて、いけるところまで一つの他者を上昇させてみた。超過。誇張。崇高なことだ!
我々は、たった一人の他者ではなく、もっと無数の他者(窒素、酸素、水、太陽……)に囲まれて生きているし、そうしたものがなければただの一時も存在することができないだろう(だからこそスピノザ的な〈身体〉の地位の与え方がある)。
ところで、レヴィナスの無限の責任について、形式的な指摘をしてみよう。
たしかにレヴィナスにおける「私」の議論では、自由意志との連関で使われるような意味においての能動性はなく、ある他の一者に対する絶対的な受動性がある。すなわちむしろ倫理における能動性と称されるべきものがある。語を見かけ上保存しつつも変形された意味が付与された、ある種の「能動性」が、倫理の条件として提示されているのだ。
しかし、例えば、私に対して他者が一人ではなく、二人現れた時点で、この倫理の条件は途端に脆弱なものになる。私はどちらを優先して、パンを差し出さなければならないのだろうか?(卑近な例かもしれないが、こうした問題がはじめて想起されたのは、子どもの頃にまたしても私の頭を悩ませた「トロッコ問題」にはじめて出合ったあのときに違いない)。優先する、という行為がレヴィナスにおいてありうるだろうか。以上より、三者以上において、無限責任の法に対する違憲状態が容易に想像されうるだろう。
とはいえ、いま私が貴方とともに考えようとしていることは、いずれを優先するのかといった功利主義的な問題ではない。
問題は、自己の本質にある愛に反して生じる、このような能動的憎悪のメカニズムである。レヴィナスに代表されるような自我殺しに抗ったロゴザンスキーは、その主著『我と肉』の中で、彼自身が自我分析と呼ぶ〈私〉の探求を開披する。
ロゴザンスキーは、レヴィナスが、迫害される能動的な私の憎悪が愛へと逆転する抵抗可能性を見誤ってしまった。と言う12。ロゴザンスキーがここで味方につけるのは、フランスの騎士(!、兵士ではなく)デカルトである。
何もかもを疑ってみよ。何もかも疑ったところで、この疑う私だけは存在するだろう。例えば、こうして私が存在していると錯覚させるような〈欺く神〉が私を欺いていると疑ってみよ。この〈欺く神〉と、〈欺く神〉にだまされている私が少なくとも在ることに間違いはない。騎士デカルトは挑発した。欺くならば、力の限り欺いてみるがよい、欺く神が欺くなら、私は在る。
かくして、〈私〉という真理は、〈欺く神〉という反真理と分離されるものではなくなる13。「今や私は、この反真理が私に異他的なものではなく、欺く〈他者〉が最終的に私自身の隠された面としてあらわになることがわかる14」〈欺く神〉は私なのだ。
ロゴザンスキーが私を構成するにあたって第一に賭けるものは、私である「肉」である。そして、この「肉」の極と極とが触れ、触れられることで触発しあう「交叉」である。極めて孤独だ。
能動的憎悪の条件は、絶対的な孤独である。孤独であるとは、触発するものが何もないことではない。孤独とは、責任の関係がないこと、債務者と責務者の関係でないことなのだ。この負債は一旦よそにおいて、肉の次元を見ていこう。
¿
フッサールは『デカルト的省察』において、「デカルトの誇張的懐疑15」にも似た方法で、私の延長属性を身体(Körper=corps)と、肉(Leib=chair)とに戦略的に区別した。
ロゴザンスキーは、フッサールの遺産として「肉」を引き継いで、肉こそが自我であると主張する。ロゴザンスキーが評価するのは〈始まり〉のデカルトであって、〈途中〉のデカルトではない。デカルトは、誇張された懐疑の方法で、確かに真理と反真理との両方が私の条件であることを〈始まり〉において明らかにしたが、この絶対的な懐疑はその後あっさりと捨てられ、究極の完全体である神の無限の善性……、すなわち信仰に舞い戻ってしまう。
これは結局は、あの広い社会における超越(論)化され擬人化された神そのものである。デカルトが幾たびも槍玉にあげられるのは、コギトのラディカルさよりもむしろ、こうした信仰のせいであるように思われる(逆に言えば、コギトのラディカルさは常に色褪せては芽吹き、その度に欺き、その度に私に真理と反真理を与える)。
信仰ののちに、「そして自我は、その真理を奪われて、〈他者〉の超越性に全面的に服従することにな」り、前回で書いたようなバトラーとともに袋小路に辿り着くことになるだろう16。ああ、パルメニデスの自殺である(それほど重要なことではない。パルメニデスについては、Wikipediaを見てみよう)。
フッサールのエポケーなる発明は、このような局面で画期的なものとなる。こうした超越を(括弧)に入れ、隔たりは隔たりのままでひとまず宙吊りにしておくエポケーによって、この神を、超越を一旦は機能停止にさせる(こうした現象学的還元を、私はスピノザに配慮しながら捉えたいと考えている。狭い社会、自己、外部の物、自然。(こうして()に括って語って注釈をし続ける、無際限なエクスキューズは、括弧にいれたからこそなんとなく許される、エポケーとはそういうものだ)。
私は椅子に座りこの文章を打ち込んでいる。椅子が尻の皮膚に触れる感覚を得る。私は椅子そのものを知覚するのではなく、この椅子とは別の椅子を思い出す。この椅子はOKAMURAのオフィスチェア、黒の「シルフィー」だ。私には、シルフィーの黒くてふかふかしたクッションそれ自体(という超越的なもの)が感覚されるのではなく、さらに細分化された、この沈み込む感覚、尻が包み込まれるような印象を感じる。椅子という他者の触発を通して、尻が包み込まれるという身体の変状を被り、私の姿勢は瓶ビールのカゴを裏返した、椅子とは呼べないものに座った時よりも快適さを得る。私は喜びを感じる。エポケーで呆けつつ、シルフィーに座って書いているあいだ、私はこの椅子とともにスピノザ主義者である。と多くの反論を一旦脇におきつつ、試しに言ってみてもいいだろう。このエポケーにおける外部の物の諸感覚が、スピノザが感じていた感覚とそれほど遠いものだとは考えない。他者が私を触発するのだか、私が私を触発するのだか……。他者だ、外部の物だ。とはいえ超越から抜け出して内側(?)に神=自然が在る。
まあそりゃそうだ。椅子は椅子であって、私ではない。椅子は私に椅子それ自体という何か超越的な物を与えたりはしない。私は椅子ではない。
だが、私のものである肉が、自我=肉が、私自身に触れるとき、私は私が触れたし、触れられたと感じる。私は私である。
私は長い時間、キーボードを叩いている。時折指を鳴らす。親指を折り曲げて、他の指で包んで圧迫する。私の指が、私に触れる。与えるものと、与えられるものとが一致する。こうした肉の極の相互の関係が、私を構成するとして、メルロ゠ポンティが交叉と名付けた現象である(だがそれは、その語が保存されて使用されるだけであって、私の肉が世界の肉と同一であるといった、超越主義、奇妙な肉主義とはまったく異なる)。ロゴザンスキーの肉による真理の開披とは、「交叉を通じて、私の肉は自らを発見し、それ自身を認め、自分の諸々の極それぞれのうちに自を探査する。私の肉のこの露呈は、まさに真理の出来事、つまりアレーテイア[開披]である17」真理の真理!
反復する……。私は長い時間、キーボードを叩いている。指輪を嵌めた指から、特別痛みを感じるわけではないのだが、違和感を感じる。私は今、その一本の指だけ、確かに私の肉ではあるものの、なんだか不気味なものであるように感じてきている。他人の手のようである。指輪が触れている円状の皮膚のみが他人のもののように感じるわけではない。幾ばくかの疲労を感じて、あくまで微かにだが、思うように動かなくなったこの指が、指輪のようにまるで着脱可能なものに思えてくる。
ロゴザンスキーの先の引用文には続きがある。「私の肉は全面的かつ決定的な仕方で自らを露呈させるのか、私の肉の一部はこの暴露に抵抗するのではないのか、いずれにせよ自我は初期の盲目性へと引き返してしまうのではないのか、これが問われるべきことになる18」真理は、開かれ、披露されるのか。それとも暴露か?
この交叉は、私が私であるというこの感覚を単純に構成するわけではない。まさに、憎悪が問われるべきことになる。ロゴザンスキーが言う憎悪のメカニズムは、端的に言えば交叉の危機であり、それは「残りもの」による「取り憑き」である。どういうことか。私の肉は確かに私であり、自我であるのだが、この中には私の肉からどうしても切り離せない残余、秘所である異他的な要素がある。「私は今後、残りものと呼ぼう19」ロゴザンスキーの仮説は極めてシンプルである。自我=肉は確かに私であるのだが、肉の次元にある残りものがあると言う。デカルトを襲った欺く神、悪霊は、どこからやってきたのかはわからないうえに、どこへ去っていくのかもわからない。それにも関わらず、真理と反真理を与えてくれる。悪霊は、私の条件なのである。悪霊は私を触発し、私に取り憑く。私に対して異他的であるにも関わらず、それは私である。「私は、これを取り憑きと名づける20」かくして、私という真理=愛、私である反真理=憎悪は、いずれも〈私〉なのである。ロゴザンスキーの主張は若干、狂っていると思う。私であるもののうちの、私でない他者に原理的に錯覚される、ある一つの項を設けるという点で。パルメニデスなら自殺しかねない。
悪霊は私である、欺く神は私である。ロゴザンスキーの主張はこうも言い換えられないだろうか。
悪霊は私である、故に私は孤独である。
スピノザ的な自己、外部の物、自然の三角回路のうち、一旦は自己にフォーカスアップをして、「自己」の中に残りもの(と呼ぶことにした)である「外部の物」を設ける。この構成によれば、自己はひとまず孤独である。何故ならば、自己と残りものは債務者-責務者の関係にないからである。江川がアルトー=スピノザから引き出した、能動的憎悪=残酷の条件がここに整っている。
¿
フロイトが提示した仮説、「死の欲望」については、スピノザには見出し難い。と再三申し上げた。何もこれは、フロイトの快原則の彼岸が全く無価値であることを意味しない。フロイトはある意味、さしあたりの観測範囲では、それほど間違っていないのだから。
フロイトだって、欲望の愛と死の「二元性」は、ある種の神話である、と言っている。まあいい。提唱者フロイトにせよ、この死の欲望は攻撃性の変奏として捉えられているわけだが、我々が手につかもうとしている憎悪は、破壊欲ではない。
死の観念を曲げるにあたって、憎悪を、ある俗的な意義での破壊と捉えるとどうなるか。単なる破壊があるだけであって、破壊された後には何も残らない。変身も何もないだろう。破壊後の未来が欠けている。タナトスに賭ける際には、能動的ニヒリズムに身を置きすぎないでいることは困難である。フロイトの仮説を忌避するのは、ひとまず破壊し尽くしたあとの、その貧相さがやや惨めだからにすぎない。「この点に関して、スピノザはフロイトよりも優れた案内人となる21」とロゴザンスキーは言う。スピノザは、喜びと悲しみとの交代を自己の身体の触発に則して、見事に分析したために確かに見事な案内人なのである。「あらゆる二元性を拒否することによって、スピノザは、同じ対象に対する愛と憎悪の共存、愛と憎悪の相互転換を、難なく説明できることになる22」だが、ロゴザンスキーにとって、結局のところコナトゥスがひっかかりとなり、スピノザは単なる案内人でしかなく、最後まで付き添ってくれるわけではない。「スピノザは、「能動的な」憎悪の可能性、外的原因なく生じて容易には愛へと変わらない内在的な原憎悪の可能性を考えることができなかった。彼は、憎悪から生まれる悪しき喜びの可能性、根本悪であるあの死の享受を視野に入れることができなかったのである23(強調ササキリ)」確かに、外的原因なくして生じる憎悪の可能性というものを、ただ『エチカ』のみから、〈別の身体へ〉の配慮もなしに取り出すことは困難だった(私は、ロゴザンスキーはむしろ意図的にこのような読解を避けている気もしているが)。困難だっただけである。江川にとっても、喜びの増大が至福へと至る道を築いたスピノザに対して、逆向きの悲しみの増大が残酷へと至るアルトーが必要だった。欺く神があり、私が在る。スピノザの至福があり、アルトーの残酷がある。私はスピノザであり、アルトーである。この関係は、デカルトのものではなかろうか。
そういうわけで私は、部分的にはロゴザンスキーに同意しよう。ただアルトーだけに生じうるのではなく、まさに私において(ロゴザンスキーがスピノザのこの語に触れることはないが)、残酷が、残りものの取り憑きによって生じるだろうということを。
能動的憎悪は私=肉=自我に、そもそも生じうるだろう。かくして、〈別の身体へ〉、自殺=変身がより私の身近なところへやってくる。
¿
だが、もっと注目すべきなのは、ロゴザンスキーもまた、江川と同じくスピノザにアントナン・アルトーを付け加えるところだ。さらに彼のアルトー評価は極まった半端さを見せている。
「アルトーにとって、〈存在〉とは死の脅威、「一種の死刑判決」である。[…]アルトーはわれわれに呼びかける。「存在することに耐えられない」始原的な身体-私、〈存在〉の手先になることを受け入れないこの身体-私を思考せよ、と。この計画を達成するため、[…]アルトーは狂気を通過しなければならなかったのである24」とロゴザンスキーは指摘する。あくまで通過するのである。レヴィナスと事態は似ている。レヴィナスは、「存在する」と語り、存在し始めた途端に生じる無限の責任を「存在する」ではなく「存在するとは別の仕方で」、と副詞で終わらせるレトリックによって、表現した。これにより、無限の責任、すなわちレヴィナスの言う倫理は、存在よりも手前に留まるのである。第一の学は、存在論ではなく倫理になるのである。アルトーは、作品によって、身体の再構成をしようとした。
ともかくそれはアルトーにもあった、だが帰還した、というわけである。ロゴザンスキーは、アルトーを狂気の詩人、という英雄に仕立て上げたりはしない。
彼に言わせれば、むしろその狂気からもう一度還ってくる狂気への抵抗があったからこそ、アルトーは稀有なのである。アルトーは狂い、病院にぶちこまれ電気ショックを浴びまくり、幾度も死んだ。そして帰還した。ロゴザンスキーは、アルトーをただの狂気にさせるような読みには抵抗を示す。狂っていた、だがまた戻ってきた。
確かに、そうだ。
注意されたいが、ドゥルーズ=ガタリに付き添った江川が、〈器官なき身体〉に生成変化しようとするとき、何も江川は通常の意味で死のうとも、狂気に陥れと言っているのでもない。当たり前である。生き延びることが重要だからだ(ここで私は「なぜ生き延びることが重要なのか」については答えていないが)。
アルトーは、ラジオ放送(『神の裁きと訣別するために』)で、たった一度、「corps(身体)……」の後のいくらかの合間の呼吸の後に「sans organe(器官なき)」と言った。そう、むしろ、〈身体 器官なき〉と言った。
身体の再構成の合間である。この合間について、ロゴザンスキーも江川も、それほど意見を異にするとは私は思わない。「[この合間は]身体から諸器官を分離する時間ではなく、有機的身体において非-有機的な〈器官なき〉が実在的に発生するような或る〈合-間〉である25」と江川は言った。仮にこう言ってみよう。一方で、概念化された英雄アルトーは、自己の身体の本質を愛する〈肉〉と、〈肉〉の内にある自己の身体の本質を嫌悪する〈残りもの〉との闘いを繰り広げることで苛烈な残酷を上演した。他方で、概念化されすぎていない作家アルトーは、死なない程度に〈別の身体へ〉を希求し、そうできた。
「肉は、私が理解する限りでは、ドゥルーズにとって重要な『器官なき身体』とそれほど違ってはいない26」とにもかくにも、アルトーが「特殊な治療法」を見出したと言う必要があるだろう。私は、一旦のところ、アルトーを一つの中途半端さの中に位置づけ直したいと思う、置いていかれないように。
必要以上に疲れてはいけない。とアルトーはいった。器官を棄て、死を経験し、新しい身体へ変身したにせよ。〈疲労した骨〉に基づいて文化を築くにせよ。分裂して、もう一度生きなければならない。身体があると知りつつ、〈器官なき〉と棄てなければならない。身体があると知ることと(合間の前の〈身体〉)、それから諸器官を棄てるまでの時間(〈器官なき〉と述べるまでの合間)、というような普遍的な時間形式が問題なのではない。たしかに〈私は思考する〉と〈私はある〉との合間にとある時間があり、この時間のうちに〈私〉と〈自我〉は引き裂かれているのだが、一方でこの分裂、この差異の総合が人間精神を構成するのである。このことは、思考属性としての精神が、延長属性としての身体の本質そのものではなく、身体の変状を知覚することと表裏一体である。憎悪のメカニズムにおける〈身体 器官なき〉に対して、(残りものを含む)肉という語を保存して宛てがうことはそれほど問題ではない。
錯乱の場。疲れ果てた俳優の身体には特殊な治療法の基礎原理が必要なのだ。疲れ果てた身体を、もう一度生きなおすことができるように。そこにはもとの器官はなくてもいい。別の身体へ。私とは不死である。
狂気のロマン主義に陥らず、だが、決して通常の意味では死なないこと。狂気とは作品の不在である、とフーコーは言った。確かに、ある時期において、アルトーはいき過ぎた。だが、〈私〉と〈自我〉を引き裂きつつ、〈自己〉を構成するところに作品が生まれる。人称的なものの、非人称的な、いや、前人称的な再構成……。
「叫びは、[…]身体を、正気に満ち、自分の内壁を閃かせ、自分の力能と能力と声を本当に沸騰させるあの状態へともたらす能力をもっている[…]その状態には一年もの努力は要しないが、一分で足りるということでもなく、意志と感性の常軌を逸した消耗が求められる27(強調ササキリ)」と、アルトーは帰還後の、死の一年前ほどの時期のノートに、書き記した。叫びとは、新しい身体への移行の体験のことだ。この呼吸は、それほど長くはないが、無論一瞬でもなく、だからといって短すぎることもない。感性の消耗がある。だが疲労した骨はある。消尽。だが自己はまだある。文化を築く。骨というよりもむしろ、枠。これまでのところ、肉が柔らか過ぎたことはない。疲労した骨は、それほど肉と遠くない。もはやどちらでもいいのだ。骨髄でもなんでも……。
自殺=変身は、難儀である。ただし、幾つかの変身を、私は観測することができる。これは、イケる。残酷としての変身では、死なずに死ぬことを、原理的に孤独に行う。疚しい良心、責務者-債務者、応答責任の関係にない形で、私が、私である異他的なものと共に孤独になること。Leave Two alone…。このaloneとはこの意味で捉えられるようになる。
¿
「ニーチェはよく知っていた、自らを不死のものとして肯定するため、[…]「生きているあいだに幾度も死ななければならない」ということ、最高の歓喜のなかで再び生まれるためには、極度の絶望に到る苦悩の段階を経ていなくてはならないということを28」とロゴザンスキーは言った。だが、ニーチェは最後には帰還しなかったが……。むろん、私が極度の絶望、能動的憎悪、残酷に、完全に取り憑かれてはいけないのだ。段階を経るにせよ。恐怖とは別の仕方で。
とはいえ、身を挺して不死の実験を行ったニーチェのレポートだけは受け取っておこう。
倫理のひとつの条件を考えたい。
ニーチェは、『道徳の系譜』で道徳がいかに発生したのかを説明している。健忘の激しい人間獣は、何か約束をしても、責任を取ることができない。約束を忘れるからだ。そして、まずいことが起こる。約束をされた者は、処罰を与える。その苦痛によって、もはや約束をするものは、忘れたくないと思う。これが人間獣の記憶の能力であり、「人間」となる。人間は、約束は忘れたとしても、苦痛を与える当のものだけはしっかりと記憶し始める。苦しかったということだけは覚えている。かくして責任という道徳が発生し、こうした苦痛の内面化、責任という罪悪感の肥大化が疚しい良心を発生させる。
責任は約束から生まれる。処罰により約束と十分な記憶能力が賦活され、主体性が生じる、というわけだ。これは道徳の条件である。私は前稿「俺、ササキリ。死の観念を曲げる準備をする。」で、バトラーが、ニーチェが説明した道徳の条件としての処罰の光景を、倫理の条件として取り込んでしまった。と指摘した。
無理もないことである。『道徳の系譜』において特に「約束」が記述された第二論文は、「約束することのできる[約束することが許された]29動物を育成すること、──これこそは自然が人間を眼中において自ら課したあの逆説的な課題そのものではなかろうか?30」という謎めいた問いかけからはじまる。謎とは、何が逆説なのか、である。約束をして、責任をとって、罪悪感とニヒリズムが蔓延する社会を成り立たせる動物を育成すること、これでいいではないか? むろん、そうではないってわけだ。
確かに責任と約束における道徳の系譜は語られるが、以降、逆説的な課題としての、約束することができる動物とは何者なのかが多く語られることはない。実のところ、この約束することができるとは、私が他人に対して負債を負うことではない。
私はこう解釈しよう。処罰なしに、私が私に対して約束するという意義は、孤独になることができるという意義に他ならない。
あらためて、逆説とは何か。忘却による責任の破棄と、忘却に抗う記憶による責任─疚しい良心の醸成とがある。忘却をしなければ、無限に責任を負って、疲労から帰還不可能になってしまう(死への恐怖、死への傾向にまるっきり征服されてしまう)。忘却とは、逆説的に、健康の条件なのだ。この意味で、特異な私と、他者ではない私との不思議な、私を責任のない仕方で記憶する約束は、逆説的に、責任─外の出来事なのだ。私はほどほどに忘却する。まるでデカルトの白痴のように。
ニーチェはスピノザの身体の活動力能の増減と対応した、喜び/悲しみの感情に注目して、こう書く。「突然に刑罰に見舞われた悪行者らが幾千年来おのれの〈犯行〉について感じてきたものも、スピノザのこの感懐と異なるものではない。つまりそれは、「思いもよらぬまずいことになったものだ」という感じであった。けっして、「ああしたことをなすべきではなかった」[=良心の呵責]という感じではなかった31」と。
こう解釈してみよう。まず倫理的な主体を構成するものにとっては、身体にとってよい/わるいがあり、伴って精神に喜び/悲しみがある。道徳の条件としての良心の呵責などなく、倫理の条件には善/悪などないのだ。まさにスピノザではないか。
ニーチェの最初の問いかけにおける「約束ができる」とは、ただの人間獣から人間への移行ではなく、人間から超人への移行の問題なのであって、この育成は、道徳的な責任/約束の達成ではなく、非-責任/約束という倫理の条件なのだ。これはひとつの健康の条件である。
ここで再び、レヴィナスの無限の責任の不健康さを思い出そう。レヴィナスにおける「私」の他者に対する無限の応答責任の、極まった受動的な能動性は、私の秘所(反真理、欺く神、悪霊、残酷への意志)への私の応答責任なのだ。通り過ぎに言ってみるが、デリダの「秘密に応答責任を負う32」、という奇妙な言表は、ニーチェが問いただした、約束-無責任の主権的個人そのもののこのことでなかろうか。
¿
異他的なものに完璧に征服されずにいたアルトーの作品は、人生の合間に精神病によって止まりかけたものの、彼が帰還することでまだ書かれたことによって、世界に在る。一方に英雄アルトー、他方に作家アルトー。
孤独のうちで、私は私であるものに触発されて、私は死を享楽する。変身の実践の一つは、平凡ながら、こうした強度をもった言葉を、記号を、作品を残すことだろう。私を排除する、能動的憎悪、取り憑き、残酷は、私の条件である。それはもはや仕方のないことだ。だから私は、作品へと折り返す。作品の署名は適当に済ませておきつつ。人生においてその死の経験をするのではなく、あくまで作品においてそうした体験をひとまずのところ済ましておくのである。「死」、「私」、「憎悪」は全て倫理の条件に関わり、倫理の条件とは、私が死なない程度にという配慮がある限りにおいて、中途半端なものなのだ33。道徳は極端すぎる。
死の観念を曲げるにあたって、私と憎悪の観念を曲げた。さて、記号を曲げる必要がある。
脚 注
- アントナン・アルトー『カイエ アルトー・コレクションⅢ』(荒井潔訳、2022、月曜社、p.359.) ↩︎
- 江川隆男『残酷と無能力』(2021、月曜社、p.47.) ↩︎
- 江川隆男『アンチ・モラリア:〈器官なき身体〉の哲学』(2014、河出書房新社、p.115.) ↩︎
- 江川隆男「骨と血からなる〈非-存在〉」(2017、立教映像身体学研究、5; 108-117. https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/record/14796/files/AA12607699_05_14.pdf) ↩︎
- 私は、ここではドゥルーズ=ガタリが『哲学とは何か』で書いた概念、概念的人物について、まだ立ち入ることができない。 ↩︎
- ポール・リクール『他者のような自己自身(叢書・ウニベルシタス)』(久米博訳、1996、法政大学出版局、p.437.)。本書のソクラテス的アイロニーを響かせた最後の一文である。 ↩︎
- エマニュエル・レヴィナス『存在の彼方へ』(合田正人訳、1999、講談社、p.177.) ↩︎
- 『存在の彼方へ』、p.257に「主体は対格としてあり、存在のうちに頼みの綱を見いだすことなく、『パルメニデス』の第一仮説に言う〈一〉さながら、存在から放逐されて存在の外にあり、根拠を知いている。まさに「自己に還元され」、それゆえ条件を欠いているのだ。みずからの皮膚のうちにあるのだ。とはいえ、主体は一個の形式のもとで静止しているのでは決してない。みずからの皮膚の内なる痛みたる主体は自己を詰め込まれ、自己によっていわば閉塞し、自己自身に圧しつぶされて窒息するのだが、主体にうがたれた換気口はなかば塞がれており、それゆえ、主体は自己からの離脱を余儀なくされ、ありったけの空気を吸い込みつつも、力つきて自己を手放し、ついには自己を喪失するほかない」
レヴィナスにとって自己は、自己がそう欲望することなしに、あらゆる受動性よりも受動的な受動性において、他人のために身代わりになるのである。
『パルメニデス』におけるロジカルでソフィスト的な〈自殺〉はそれはそれとして、アイロニーとして受け取っておこう。
Wikipediaを見て何が悪い?→https://x.gd/eaQIc ↩︎ - 『存在の彼方へ』、p.342. ↩︎
- 『存在の彼方へ』、p.286. ↩︎
- レヴィナスの『存在の彼方へ』を「誇張」の方法があると指摘したのは、ポール・リクール『別様に:エマニュエル・レヴィナスの『存在するとは別様に、または存在の彼方へ』を読む』(関根小織訳、2014、現代思潮新社)である。『存在の彼方へ』の対決は倫理学を存在論の上位に位置付けることなのであって、倫理的に語ることを存在論の外側で、いわば倫理に固有のものとして定式化することが目標であり、その概念的戦略として、主体の代わりに身代わりを設定し、主体から逃れた語ること=息切れ(前言撤回とも表現される)、存在論から逃れた「存在するとは別の仕方で」を模索するのである。リクールは特に文彩に注目して「教的とはいわないまでも宣言的といえる口調で述べられており、強迫的とはいわないまでも執拗なる誇張法という文彩の使用で保たれている。口調と文彩にかかわるこの二つの特徴によってこそ〈語ること〉の倫理化を私は性格づける」(『別様に』、pp.27-28.)と評し、誇張法に注目する。「隣人による脅迫においては、記憶、修史を通じて私が集約した先験的に支配しうるいかなるものよりも古き過去のうちで、始まり以前の時間のうちで、触発の打撃が外傷としての衝撃を刻み続けるのだ。」(『別様に』、pp.32-33.)とのリクールによる整理によれば、打撃や外傷、隣人の脅迫、命令がレヴィナスの言うところの「顔」である。 ↩︎
- 「ハイデガーの立場はレヴィナスの立場と対称的であるように思われる。デカルト的自我のうちに、ドイツの思想家は征服的な力への意志しか見なかったのに対して、『存在するとは別の仕方で』の著者は、反対に、迫害者に対抗することのできない「自己へと追い詰められた」自我の絶対的受動性を称揚する。両者とも、自我について、自我の誕生の逆説について、思い違いをしている。被迫害者の悲嘆が肯定へと逆転する、自我の受動性と自我の抵抗との分離不可能な統一性を、二人は見誤ったのである。」ジャコブ・ロゴザンスキー『我と肉:自我分析への序論』(松葉祥一・村瀬鋼・本間義啓訳、2017、月曜社、p.146.) ↩︎
- ドゥルーズ=ガタリは『哲学とは何か』、p.109の「概念的人物」という章で以下のような記述をしている。「デカルトのケースにおいて、創造されたコギト概念と、前提された思考のイメージのほかに、何か他のものが存在するのだろうか。いささか神秘的な他のものが、実際に存在するのである。それは、時おり出現し、あるいは透けて見えたりするものである。しかもそれは、前概念的〔内在〕平面と概念とのあいだで行ったり来たりする、中間的な、或る朧な存在をもっているように思われる。それは、さしあたって、〈白痴〉である。(私)と言うのはまさに彼であり、コギトを発するのはまさに彼であり、主観的諸前提を抱え込んだり平面を描いたりするのも、まさしく彼である」(強調ササキリ)。この点の分析に関しては、福尾匠『非美学:ジル・ドゥルーズの言葉と物』(2024、河出書房新社、pp.340-350.)を参照されたい。
また、福尾は同書でデカルトの〈私〉の行為遂行性を分析している。また、ロゴザンスキーも同様である。「厳密には、デカルトの「私は在る」を行為遂行的と呼ぶこともできるかもしれない。ただし、「私は在る」を言語操作と同一視してしまう危険性がないとすればである。それは、「私」を言う行為に限定されない自我の可能性を恣意的に切り捨ててしまって、「私は在る」を、この言葉を言表する発話行為に還元してしまう危険性である。」(『我と肉』、p.151.)。なお、行為遂行性と自由意志(道徳主義、広い「社会」)との結託には常に注意する必要があるだろう。「彼の最初の発語行為によってたしかにこうした発語行為における一つの系列が成立するが、しかしそれ以上に重要なことは彼の発語内行為を媒介にして私の自由意志が形成され発揮されうるという点にある。このことは、最初の彼の発語行為がそもそも彼の自由意志に依拠しているなら、その発語効果によって今度は私の自由意志そのもののうちに特定の行為に関する因果関係が生起することになる。しかし、これは、実は不合理である。というのも、自由意志は、その都度の絶対的な自由のもとでの第一原因でなければならず、諸々の自由意志による決定の連鎖といったものは、それ自体が矛盾した表象以外の何ものでもないからである。」(江川隆男『内在性の問題』(2024、月曜社、p.470.))
ロゴザンスキーが自我殺しに抗って、〈私〉こそ真理であるというときと、江川が〈自我〉や〈私〉ではなく、〈自己〉があるのだというときとの狙いにそれほどの差はない。だがロゴザンスキーは、デカルトは「私」と言い、スピノザが「私たち」と言うことを不満に思っているようだが、これはナイーブすぎるように思われる。ロゴザンスキーの肉の議論には言語や記号の次元の考察がほとんど抜け落ちているが、このナイーブさが原因であると私は考えている。私は、記号の観点から、ロゴザンスキー『我と肉』には留保をつけておく。 ↩︎ - 『我と肉』、p.149. ↩︎
- ポール・リクール『他者のような自己自身』、p.408「[フッサールが『デカルト的省察』の第五省察において]省察する自我はそこで、自己のものへ還元されるこの経験において、それ自身の措定と同じく必当然的な措定として、他人を措定することを要求するものを識別するために、日常的経験が他人に負っているものすべてを中断し、したがってそれをすべて疑わしいとすることからはじめる。この思考の動きは、デカルトの誇張的懐疑にまったく比較しうるものである。ただしその動きは、いかなる悪しき霊[=欺く神]の仮説にももとづいていない。」 ↩︎
- 『我と肉』、p.199. ↩︎
- 『我と肉』、p.232. ↩︎
- 同上 ↩︎
- 『我と肉』、p.254. ↩︎
- 『我と肉』、p.263. ↩︎
- 『我と肉』、p.362. ↩︎
- 同上 ↩︎
- 『我と肉』、p.363. ↩︎
- 『我と肉』、p.68. ↩︎
- 『内在性の問題』、pp.476-477. ↩︎
- 『我と肉』、p.226. ↩︎
- 『カイエ アルトー・コレクションⅢ』、p.351. ↩︎
- 『我と肉』、p.377「不死であることは高くつく。なぜなら、生きている間に幾度も死ななければならないからだ。」フリードリッヒ・ニーチェ『ニーチェ全集15:この人を見よ・自伝集』(川原栄峰訳、1994、筑摩書房、p.138.) ↩︎
- 約束することが許される、と解釈する向きについては、以下を参照。ただし、谷山のような、自らへの約束を、私の私に対する(通俗的な)応答責任として捉える解釈については、留保をつける(谷山弘太「「約束することが許される」ということ:ニーチェ『道徳の系譜』第二論文における「主権的個人」についての考察」(2019、倫理学年報、68; 127-140. https://www.jstage.jst.go.jp/article/ethics/68/0/68_127/_pdf/-char/ja))。 ↩︎
- フリードリッヒ・ニーチェ『道徳の系譜』の第二論文「〈負い目〉、〈良心の疾しさ〉、およびその願いのことども」の最初の一文。(フリードリッヒ・ニーチェ『ニーチェ全集11:善悪の彼岸 道徳の系譜』(信太正三訳、1993、筑摩書房、p.423.)) ↩︎
- フリードリッヒ・ニーチェ『ニーチェ全集11:善悪の彼岸 道徳の系譜』、p.461. ↩︎
- ジャック・デリダの講義録のタイトル「Répondre-du secret.(応答する─秘密について/秘密に責任を負う)」のダブルミーニングを汲んで、西山雄二は「秘密に応答責任を負う」と訳している。このタイトルには、秘密に返事をすることと、秘密に責任を負うことの二重の意味が込められている。
https://youtu.be/PzQ1OB2KQnA?si=KvYUCxBYhZN1UYbn
https://researchmap.jp/yujinishiyama/presentations/46113510 ↩︎ - 千葉雅也『動きすぎてはいけない:ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(2017、河出書房新社、p.377. における「半端な器官なき身体」という概念から借りてきた語である。 ↩︎