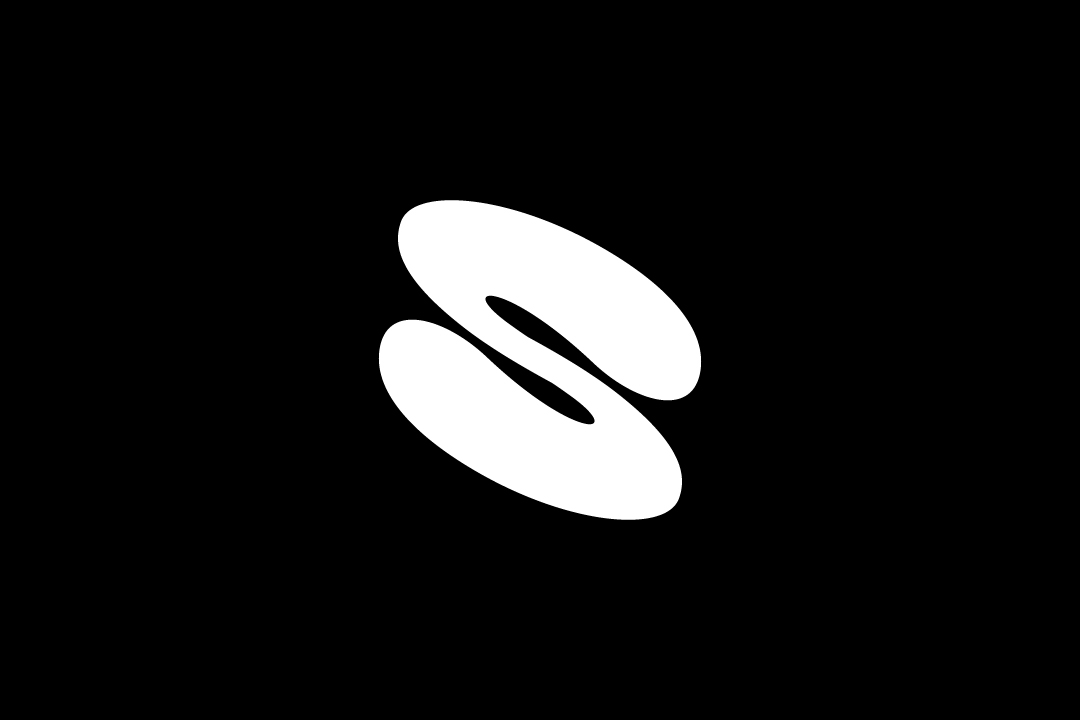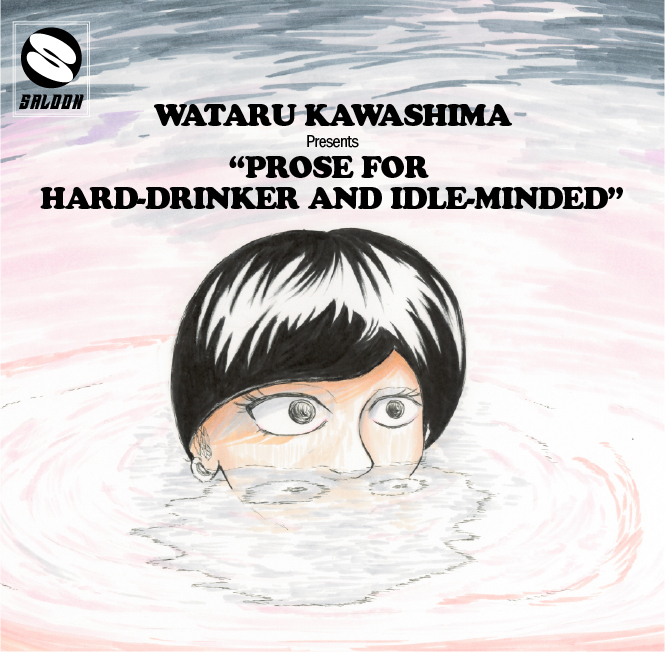人と飲んでいる時にはホッピーを頼まないようにしている。
あれは飲み過ぎてしまう。
大学生の時に学んだことだ。
今もそうだが、大学生の頃はできるだけ安く飲みたかったし、あるいはもつ焼き屋なんかに入った時にはホッピーを頼むのが、レジャーの一つと言うか、醍醐味みたいなものだと考えていたので、メニューにあれば積極的にホッピーを頼んでいたのだが、大抵その場合は、店の会計時には既に記憶がなく、二軒目以降のことを憶えていないのは言わずもがなである。
僕は記憶を保持できなくなってからも、眠ってしまうようなことはなく、自動操縦で動き続け、そしてなぜかオートで飲み続けてしまう人間なので、周囲に迷惑をかけたことは数え切れないし、まきちらした吐瀉物の量も計り知れない。
当時は飲み方を知らなかったということもあるだろうが、これは酒のチョイスにも原因があったようで、どうもホッピーを頼むと、気を付けていたつもりでも、知らず知らずの内に飲み過ぎてしまうらしい。
しかし、まあ、今でも一人で飲むときにはホッピーをよく頼む。
やはり安さが魅力だ。
最終的に自分のキャパシティを越えて、必要以上に飲んでしまっているわけだから、逆に会計がかさんでいるような気もするのだが、メニュー表を見た時に、サワー系が390円、生ビールは550円とか、そこらの価格帯の店に行くと、ナカ250円なんかでおかわりできるホッピーにどうしても目が行ってしまう。ホッピーの文字が光って見えるなんてことはないが、それを差し置いて他のドリンクを頼むことに、軽い抵抗を感じてしまう。
人と飲むときは一々値段を気にしたりしたくないが、一人で飲むときにはどれだけ安く済ませるかも重要である。何なら、それが一人飲みにおける満足度に直結する。それに一人では他人に迷惑をかけるほど酔っ払うこともないだろう。
そう考えてホッピーを注文するのだが、やはりついつい飲み過ぎてしまう。
この前も市ヶ谷で一人で飲んでいる時に、例のごとくホッピーを頼んだのだが、知らず知らずのうちに飲み過ぎてしまったらしい。その日は、後に友人からの連絡を受け、幡ヶ谷のあたりで合流することになったのだが、市ヶ谷の店を出る段になって、自分が思いのほか酔っぱらっていることに気が付いた。
その店のナカ焼酎はそこまで量が多いわけではなく、提供されたナカ入りのジョッキに、満タンになるまでソトを注いでしまえば、薄いホッピーが2杯飲めて終わり、というくらいだった(もしかするとそれが一般的な量と言えるのかもしれない)。
自分はそれでは物足りなかったので、50円ほどお得に約4杯分のナカが頼める「お得中焼酎」とやらを頼んでみたのだが、これが慢心だったのかもしれない。
ソト1本に対してその店が推奨する5杯分のナカ(最初のホッピーセットの1杯分+「お得中焼酎」の4杯分)は流石に量が多かったらしい。
しかし飲んでいる間は、そこまで無理をして濃い酒を飲んでいる気にはならなかった。
ホッピーは気付かないうちに濃くなる。
これは僕の貧乏性のせいでもある。
こちらに濃度が委ねられており、基本的に濃く飲めば濃く飲むだけ「お得」になる(店側は甲類焼酎をそのまま出しているだけなので、それが「お得」と呼べるのかは疑問だが、大事なのはこちらの感じ方である、店側の事情など知ったことではない、何ならこちらの支払う料金が安くなり、店側も楽できるなら、Win-Winの関係である)。
とにかく濃く飲めば濃く飲むだけ、僕がその店で摂取できる純アルコール量に対する会計が安くなるわけだから、こちらとしては「お得」に感じる。
もちろん、かといって必要以上に濃い酒を飲みたくはない。美味しく飲むのが大前提だ。しかし濃ければ濃いほど得となれば、そのギリギリを攻めたくなるのが人の心というものだろう。
ホッピーの優れた点は、ソトとナカの配分を多少間違えてしまっても、案外飲みやすいというか、飲めてしまうところだ。口に運ぶたび、「確かに濃いなあ」とは感じるのだが、それでも焼酎のロックを飲んでいるような気にはならない。それこそビールやサワーの類と同じペースで飲めてしまう。
以前は、9:1くらいの割合でホッピーを飲んでいる中年を見かけては、それならば焼酎のロックを飲めばいいのに。と密かに心の中で呟いていたのだが、やはりそれは違うのだ。
9:1でも飲めてしまう。その「飲みやすさ」に、ホッピーの魅力がある。
ついでにいえば、ホッピーといえば白であり、黒ホッピーは白ホッピーを飲み飽きた人間が気分転換のために飲むもの、あるいは一部の物好きのために用意された選択肢、くらいに思っていたが、どうやらそれも違うらしいと最近気が付いた。
濃い焼酎には俄然黒ホッピーである。
白では大量の甲類焼酎を相手取るのに心許ない。それこそ、9:1なんかの比率で飲むときには、ほとんど焼酎の味しかしないし、それではやはりサワーやビール類のように杯は進まない。
その点、黒ホッピーは主張が強いので、少量で焼酎の味をかき消してくれるし、何より少し混ぜるだけで焼酎に色が着くのがいい。色が着いているというだけで、「焼酎をそのまま飲んでいる」感じは大いに薄れる。
以上のことを踏まえて、むしろ白ホッピーは薄いホッピーを好むビギナー向けに用意された選択肢、いわば入門用ホッピーであり、黒ホッピーこそがホッピーの神髄と言えるだろう。
ホッピー談議が長くなったが、今回は酒の濃さについて話したいのだ。
大学生で一人暮らしをしていた頃、実験ではないのだが、まあ若者らしく自分の「ポテンシャル」を知りたかったのと、馬鹿々々しい「肝臓の鍛錬」も兼ねて、なるたけ濃い酒を飲み続けていた時期がある。
当時はウィスキーをよく飲んでいたのだが、自宅でハイボールを作る際には基本的に1:1で作り、「ボイラー・メーカー」または「爆弾酒」などと呼ばれているものの真似をして、ウィスキーを発泡酒で割って飲むことも多かった。
安ウィスキーをビールのまがいもので割って飲んでいただけなので、当然ながらその味は褒められたものではなかったが、この飲み物の優れている点は、ホッピーと同じように、それこそビールを飲んでいるようなペースで、高アルコールのドリンクを飲めることだった。
ウィスキーのロックなんかも、やはりちびちび飲む分には、いくら度数が高くてもぜんぜん酔わない。そこでガバガバ飲むと流石に値が張るし、まあそもそも、僕の体質的にもそんなペースで飲めるものではない。
そういえば、この春、兄の結婚式があったのだが、披露宴の後に、親父が学生時代から世話になっている銀座のバー(「RAGTIME」という店で、既に還暦を超えている親父が学生時代から通っていたわけだから、もう40年は続いていることになる、以前は別の場所に居を構えていたそうだが、数年前に銀座に移ったらしい)に、親父と、母方の叔母と、僕、の3人でお邪魔したのだが、そこではウィスキーをロックというか、ほぼストレートで、ガバガバと飲むことができた。
親父が入れているボトルのウィスキー(グレンリベット12年)のオン・ザ・ロックを3人分出してもらったのだが、丸い氷に少量のウィスキーが注がれ、ラベルをこちらに向けたボトルとともに提供される、というところまではいつも通りだが、そこからが少々特異で、親父はそれを瓶ビールのお酌でもするかのように、僕と叔母のグラスに、飲み切る前からどんどん注ぎ足していった。
いわゆるバーでの飲み方としては妥当なやり方ではないと思うのだが、流石にそこは親父が40年近くも通った店である。移転時には、しばらく顔を見せていなかった親父のボトルキープを、わざわざそのまま新しい店舗にまで持ってきてくれたらしい。多少の無作法は許されるのだろう。
僕は途中から記憶が曖昧だが、一時間半ほどの滞在で、3/4近く残っていたそのボトルは空ききったはずだ。
親父の飲酒量はどうかしている。
しかし僕も、その前の披露宴でも、ある程度の量を飲んでいたにもかかわらず、その時はするすると酒が入ってきて、かなり楽しく酔っ払うことができた。
その後、3人で「銀座ライオン」に移動し、唐揚げを食べながら2杯だけビールを飲み、親父は電車で家に帰り、叔母をタクシー乗り場で見送った後、僕は別件で飲んでいた友人と吉祥寺で合流し、記憶のないままカラオケオールにまで参加した。憶えていないが、もしかすると酔っ払った僕が、友人たちを無理矢理朝まで付き合わせてしまったのかもしれない。親父と叔母を含め、迷惑をかけた友人たちにこの場を借りて謝罪しておく。
しかし、この日は久々に心底楽しくて、当然ながら翌日はひどい二日酔いに見舞われることになったのだが、それを差し引いても、本当に幸福な一日だった。その後も数日間余韻が残り、あの、非日常を体験してからしばらくの、なんとなく元の日常に戻れない感じというか、ふわふわと浮き足立った状態が、かなり長いこと続いた。
ともすると、これはその日の酒の飲み方が良かったのかもしれない。不思議なことに、普段ならすぐに気持悪くなってしまう量と度数の酒を、その日は、無理をしている感覚もなく、長いこと飲み続けることができた。
そんな飲み方はなかなかできない。
僕は酒好きだが強くはないので、ウィスキーやら焼酎やらを、生のままガバガバ飲んで、毎回気分良くなれるわけではない。
友人がDJを務める、落ち着いた雰囲気のこじんまりとしたクラブに呼んでもらい、景気づけにショットを奢ってもらうようなこともあるが、そういった場面でも、立て続けに何杯も飲むことはできない。一杯飲むぶんには、キンキンに冷えた蒸留酒は、うまいし、レジャーとしての楽しさもあるのだが、何杯も連続して飲めば、ほろ酔い気分で楽しくなるよりも先に、アルコールの臭気にあてられて気分が悪くなってしまうだろう。かといってちびちびと飲むようなものでもないので、すぐさま手持ち無沙汰になって、追加でビールやらハイボールやら頼むことになる。やはり手元には常に酒があってほしい。
そういったときに、ウィスキーのロックなんかを時間をかけて飲んでいるのではなかなか盛り上がらないので、ビールやハイボールのような、グラスやジョッキに満タンに注いで、喉を鳴らして飲むことができる酒を頼むのだが、もしかすると、もう少し度数が高く、かといってちびちびと舐めるようなものでもない、いわゆる、「飲みやすい」酒というか、度数の高さを感じさせない酒があれば、より一層盛り上がるのかもしれない。
ふと思い出したのだが、誰だったか、酒に対して「飲みやすい」という表現が使われることを毛嫌いしている知り合いがいた。
日本酒に対して使われることが多い表現だが、彼曰く、その「飲みにくさ」や「癖」のようなものも含めた、酒の味が嫌いなら、そもそも酒を飲まなければいい。とのことだった。酒嫌いの人間が、「強いていえば、これなら飲める」というようなものを探し出てまでアルコールを摂取することに、どれだけの意味があるのか、というようなことを彼は口にしていたような気がする。確かにその通りで、酒が飲めないなら、無理して飲まなければいい、と僕も思う。
そういえば、僕は自分以外の人間に酒を飲んで欲しい、あるいは相手を酔わせてやろう、と思ったことが一度もない。
何なら、人と飲む際には、どちらが先に酔っ払い、いかに介抱の役目を相手になすりつけるか、あるいはそこまで露骨でなくとも、自分より酔っ払っている人間を見たときの、あの白けた、一気に酔いが醒めるような、興ざめ感を、自分が味あわずに済むように、自分はトップギアで飲みまくり、ぶっちぎりで酔っ払ってしまいたいのだ。
だから「レディ・キラー」みたいな名前をつけられた酒とも縁がなく、人生で初めて参加した合コンで、先方の一人が、大した量を飲んでいないにもかかわらず、意識が朦朧とするほどに酔っ払っていたのだが、それを見た友人から「相手のドリンクに薬を入れたのはお前か?」と訊かれたとき、なるほどそういうことが起こり得るのか、と無知と能天気を晒しながら心底驚いたくらいだ。
僕自身、酔っ払っている人間を見て「面白い」と思ってくれる層が存在することによって、何とか社会に居場所を見出している状態なので(そういった層以外で、僕を面白がってくれる人間はそうそういない)、人に飲ませようとする、あるいは人を酔わせようとする価値観には救われている部分があるのだが、まあ、それでも僕が人に無理矢理飲ませることはないし、酒を飲めない人間に対して反感を抱くようなこともない、ということは一応断っておこう。
反対に、相手が飲まないからといって、自分も飲まない、という選択肢は僕にはない。相手がシラフで、自分一人が酒を飲んでいる状態に、多少の負い目を感じないこともないが、しかし、相手に酒を飲まない自由があるように、僕にはどんなときでも・何に気兼ねすることなく、酒を飲む自由があるはずだ。飲む権利と飲まない権利は同時に認められなければならない。
しかし、飲酒という文化に付随する、そういった危うさというか、加害性というか、悪い側面については常に意識しておきたい。
話が逸れたが、とにかく、僕は僕自身のために、「飲みやすい」酒を欲している。
理由は単純で、効率的に酔うことができたら楽しいんじゃないか、と踏んでいるからだ。
もちろん、酔えば酔うほど楽しくなるとも限らないが、しかし濃い酒をグビグビと飲んでいる時の高揚感には代え難いものがある。今思い返してみても、濃い酒を飲んでいる際には、普段以上に盛り上がることが多い。それは一人で飲んでいるときでも、複数人で飲んでいるときでも同じだ。
あるいは順序が逆で、普段以上に盛り上がったがために、いい気になって普段以上に濃い酒を飲んでしまっているのかもしれないし、もしくは単に体調の問題で、濃い酒を大量に飲めるコンディションのときには、シンプルに身体の調子がいいので、普段よりもテンションが上がりやすいだけなのかもしれない。
しかし、そのどちらでもかまわない。
何にせよそこには楽しい時間と濃い酒がある。
また、翌日に二日酔いで一日動けなくなることを考えると、エネルギー保存の法則のように、プラマイゼロで幸福の総量は変わらないのかもしれない。
しかし、それならせめて、でかい花火を打ち上げたい。
急アルで死んだりしない限り、楽しけりゃなんでもいいのだ。
僕はこれからも必要以上に濃いホッピーを飲み、予定調和のように記憶をなくし、友人に絡み、翌日は二日酔いでトイレに籠ることになるだろう。
後悔するとわかっていても飲んでしまうのが酒というものだ。
僕はここから離れられない。
しかし僕は今、たしかに幸福である。