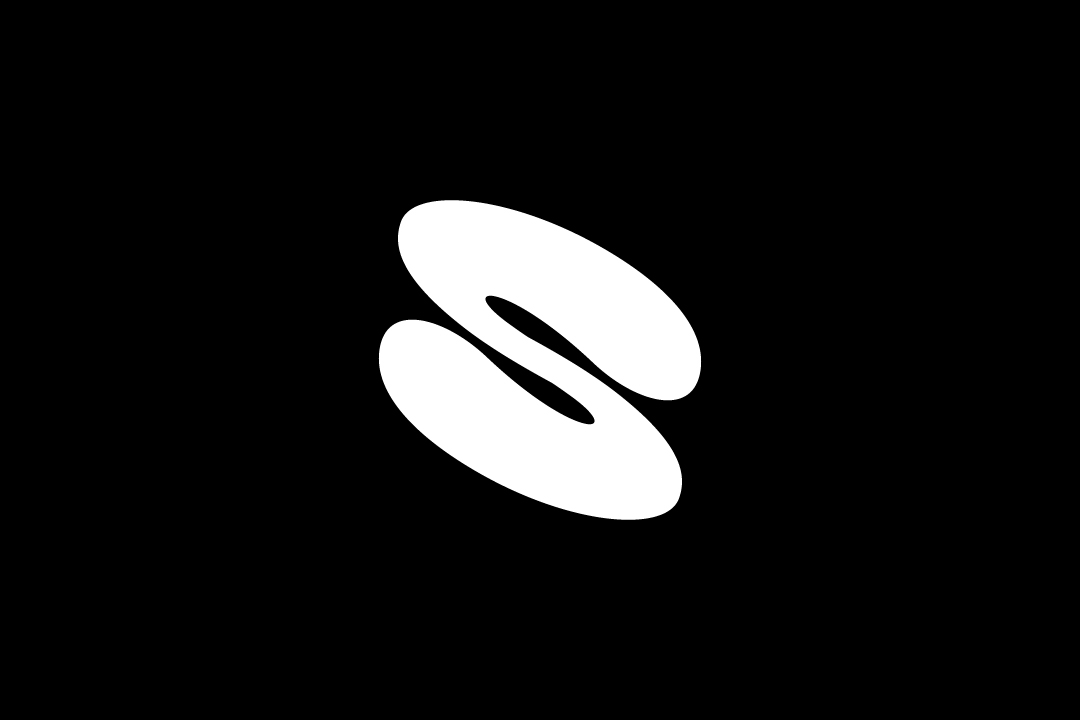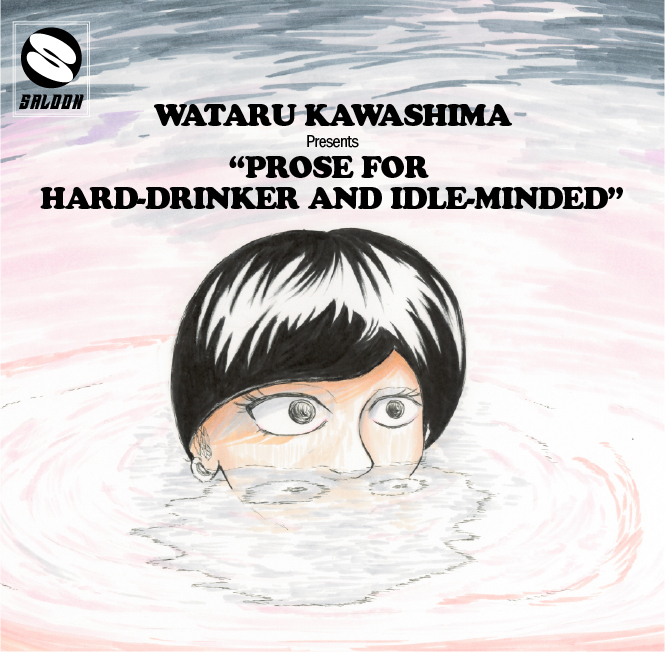以前こんな文章を書いた。
ステートメント_アルコール依存のケース🥃/川島 航|zonbipo (note.com)
わざわざ読んでもらうのも忍びないので、主張したかったことだけ簡単にまとめると、「酒は楽しく飲むものなので、わざと依存しにいって、自己憐憫に浸るような真似はやめよう。」といったところだ。
上の文章でも書いているのだが、僕は昔、ちょっとアルコール依存症気味な時期があった。そして、その頃には、酒に依存している人こそ正しい、とか、アルコールに依存してしまう人の方が真に「人間らしい」なんて思っていた。酒に依存せずに済んでいるような奴は、苦労を知らず、何の悩みもなく生きているような人間で、人の気持ちも考えないような「人非人」だ! とすら思っていたこともある。恥ずかしい限りだ。
また、これは、あからさま過ぎて恥ずかしいのだが、そこには少なからず、太宰治の影響があったのかもしれない。僕は太宰治が大好きだ。ハマった経緯もかなりあからさまで、中学生の頃に『人間失格』を読んだのがきっかけだ。
恥の多い生涯を送って来ました。
という、本編の書き出しが有名だが、そのすぐ後にくる、「自分には、人間の生活というものが、見当つかないのです」なんて文章も中学生の僕にはかなり刺さった。更に読み進めていくと、「自分の幸福の観念と、世のすべての人たちの幸福の観念とが、まるで食いちがっているような不安」、「自分には、禍いのかたまりが十個あって、その中の一個でも、隣人が脊負ったら、その一個だけでも充分に隣人の生命取りになるのではあるまいか」、周りの人間は「エゴイストになりきって、しかもそれを当然の事と確信し、いちども自分を疑った事が無いんじゃないか?」なんて文章が登場する。
周りは何もわかっていなくて、自分が誰よりもモノを考えていると思っていた(それでいて、もしかしたらそんな風に感じている自分が、一番何もわかっていないガキなんじゃないか、ということにも薄っすら気づき始めていた)中坊にとっては、クリティカルヒットの文章だった。
更にこんな文章が続く。
「そこで考え出したのは、道化でした」「おもてでは、絶えず笑顔をつくりながらも、内心は必死の、それこそ千番に一番の兼ね合いとでもいうべき危機一髪の、油汗流してのサーヴィスでした」「自分は子供の頃から、自分の家族の者たちに対してさえ、彼等がどんなに苦しく、またどんな事を考えて生きているのか、まるでちっとも見当つかず、ただおそろしく、その気まずさに堪える事が出来ず、既に道化の上手になっていました。つまり、自分は、いつのまにやら、一言も本当の事を言わない子になっていたのです」
周りを見下していたくせに、自尊心が誰よりも高かった子ども。それでも疎外されることやいじめられることを恐れて、学校でも家でも、波風立てずにボケをかまして、仲介役になろうとしていた子どもにとっては、太宰治、ひいては『人間失格』の主人公である大庭葉蔵は、自分の唯一の理解者に見えるものだった。
誰も自分のことをわかってくれない、なんて嘆いていた時期に、これだけ自分のことをピタリと言い当ててくれる相手に出会って、心酔しない方がおかしいだろう。次第に、太宰治の言葉は何でもかんでも金言に聞こえて、「自分は、空腹という事を知りませんでした」なんて言葉すら、給食を食べきれずに苦しんでいた僕のことを言っているのだと思ったくらいだ。
だから、酒に依存しているのが、人間のあるべき姿だと勘違いしてしまったのも仕方のないことだろう。
例えば『人間失格』には、こんな会話が登場する。
中から、シヅ子とシゲ子の会話が聞えます。
「なぜ、お酒を飲むの?」
「お父ちゃんはね、お酒を好きで飲んでいるのでは、ないんですよ。あんまりいいひとだから、だから、……」
主人公が転がり込んだ家で、その家主である未亡人と、その娘との間で交わされた会話だ。
また、『人間失格』はこんな一文で終わる。こちらは、主人公が世話になっていたバーのマダムのセリフだ。
「私たちの知っている葉ちゃんは、とても素直で、よく気がきいて、あれでお酒さえ飲まなければ、いいえ、飲んでも、……神様みたいないい子でした」
アル中全肯定の小説である。
しかし、僕はもう立派な大人なので、自傷的に酒を飲んで、自己憐憫に浸るようなことはない。自分の機嫌は自分で取れる。
坂口安吾が『人間失格』について、「あれはフツカヨイの中にだけあり、フツカヨイの中で処理してしまわなければいけない性質のものだ」なんて言っていたが、確かにその通りなのかもしれない。僕は二日酔いのやり過ごし方を誰よりも熟知しているつもりだ。「フツカヨイ的」なものに、今さら心酔したりはしない。
そんなこんなで、僕は酒飲みの暗い側面というか、負の要素ばかり取り上げるのは嫌なので、最近は、酒について書いている文章の中でも、明るいものが好きだ。太宰治の作品で言えば、それはやっぱり『津軽』だろう。
もちろん、『津軽』だってかなりセンチメンタルな作品で、「巡礼」なんて仰々しい章タイトルで幕を開け、以下のような会話が描かれる。
「ね、なぜ旅に出るの?」
「苦しいからさ」
「あなたの(苦しい)は、おきまりで、ちつとも信用できません」
「正岡子規三十六、尾崎紅葉三十七、斎藤緑雨三十八、国木田独歩三十八、長塚節三十七、芥川龍之介三十六、嘉村礒多三十七」
「それは、何の事なの?」
「あいつらの死んだとしさ。ばたばた死んでゐる。おれもそろそろ、そのとしだ。作家にとつて、これくらゐの年齢の時が、一ばん大事で、」
「さうして、苦しい時なの?」
「何を言つてやがる。ふざけちやいけない。お前にだつて、少しは、わかつてゐる筈たがね。もう、これ以上は言はん。言ふと、気障になる。おい、おれは旅に出るよ」
既に十分すぎるほど気障なセリフだ。
しかし、ページを一つめくれば、すぐに人間臭くて愛おしい描写が飛び込んでくる。
…(前略)…私は、東北の寒さを失念してゐた。私は手足を出来るだけ小さくちぢめて、それこそ全く亀縮の形で、ここだ、心頭滅却の修行はここだ、と自分に言ひ聞かせてみたけれども、暁に及んでいよいよ寒く、心頭滅却の修行もいまはあきらめて、ああ早く青森に着いて、どこかの宿で炉辺に大あぐらをかき、熱燗のお酒を飲みたい、と頗る現実的な事を一心に念ずる下品な有様となつた。
気障なセリフを残して旅立ってみても、結局、寒い野外を少し歩けば、すぐに熱燗のことで頭がいっぱいになる。
ちなみに、この願いは、もう一つページをめくればすぐに叶うことになる。
炉辺に大あぐらをかき熱燗のお酒を、といふ私のけしからぬ俗な念願は、奇蹟的に実現せられた。T君の家では囲炉裏にかんかん炭火がおこつて、さうして鉄瓶には一本お銚子がいれられてゐた。
「このたびは御苦労さまでした。」とT君は、あらたまつて私にお辞儀をして、「ビールのはうが、いいんでしたかしら。」
「いや、お酒が。」私は低く咳ばらひした。
すごく幸せな描写である。寒い野外を歩いてきたところに、あやうくビールを出されそうになって、「いや、お酒が」なんて慌てるのも、すごくかわいい。『津軽』は本当に面白い。
『津軽』で一番好きなシーンは、もちろんラスト、育ての親である女給「たけ」との再会のシーンだが、その他で言えば、上記のような、人間臭く、ちょっと気恥ずかしいような、こまごまとした場面が印象に残っている。
以下に引用するシーン。太宰治が酒の種類について、妙な「遠慮」をする場面が特に印象深い。少し長いが読んでみてほしい。
…(前略)…私がこんど津軽を行脚するに当つて、N君のところへも立寄つてごやくかいになりたく、前もつてN君に手紙を差し上げたが、その手紙にも、「なんにも、おかまひ下さるな。あなたは、知らん振りをしてゐて下さい。お出迎へなどは、決して、しないで下さい。でも、リンゴ酒と、それから蟹だけは。」といふやうな事を書いてやつた筈で、食べものには淡泊なれ、といふ私の自戒も、蟹だけには除外例を認めてゐたわけである。私は蟹が好きなのである。どうしてだか好きなのである。蟹、蝦、しやこ、何の養分にもならないやうな食べものばかり好きなのである。それから好むものは、酒である。飲食に於いては何の関心も無かつた筈の、愛情と真理の使徒も、話ここに到つて、はしなくも生来の貪婪性の一端を暴露しちやつた。
蟹田のN君の家では、赤い猫脚の大きいお膳に蟹を小山のやうに積み上げて私を待ち受けてくれてゐた。
「リンゴ酒でなくちやいけないかね。日本酒も、ビールも駄目かね。」と、N君は、言ひにくさうにして言ふのである。
駄目どころか、それはリンゴ酒よりいいにきまつてゐるのであるが、しかし、日本酒やビールの貴重な事は「大人」の私は知つてゐるので、遠慮して、リンゴ酒と手紙に書いたのである。津軽地方には、このごろ、甲州に於ける葡萄酒のやうに、リンゴ酒が割合い豊富だといふ噂を聞いてゐたのだ。
「それあ、どちらでも。」私は複雑な微笑をもらした。
N君は、ほつとした面持で、
「いや、それを聞いて安心した。僕は、どうも、リンゴ酒は好きぢやないんだ。実はね、女房の奴が、君の手紙を見て、これは太宰が東京で日本酒やビールを飲みあきて、故郷の匂ひのするリンゴ酒を一つ飲んでみたくて、かう手紙にも書いてゐるのに相違ないから、リンゴ酒を出しませうと言ふのだが、僕はそんな筈は無い、あいつがビールや日本酒をきらひになつた筈は無い、あいつは、がらにも無く遠慮をしてゐるのに違ひないと言つたんだ。」
「でも、奥さんの言も当つてゐない事はないんだ。」
「何を言つてる。もう、よせ。日本酒をさきにしますか? ビール?」
「ビールは、あとのはうがいい。」私も少し図々しくなつて来た。
本当は日本酒やビールが飲みたいのだが、それを言っては図々しすぎると思って、妙なおべっかを言っている太宰も面白いし、それを簡単に見透かされているのも面白い。「でも、奥さんの言も当つてゐない事はないんだ」なんて、往生際の悪さも最高だ。何より、「遠慮」した手紙を送っていながら、最終的に太宰の予想通り(予想以上)の展開になっているのが幸せだ。
ちなみに、僕も、実家に帰る時なんかに、同じような遠慮の仕方をすることがある。正月に実家で飲むときなんかは、家族が各々の手土産を持ち寄って、それなりに豪華な食卓が用意されるのだが、僕はいつも、土産物の酒は味見程度にして、大抵は近所のドン・キホーテで買ってきた缶チューハイか発泡酒を飲んでいる。そりゃ、もちろん、せっかくなら美味い酒をたらふく飲みたいのだが、僕は酒の質に関係なく、飲み始めればそれなりの量を飲んでしまう人間なので、さすがに遠慮している。兄夫婦が手土産に持ってきてくれる、ちょっといい日本酒だって、720mlくらいだったら余裕で一人で空けてしまう。それはさすがに非常識だ。それくらいのことは僕にもわかる。だから、「今はチューハイの気分なんだよね」とか、「何だかんだこの発泡酒が美味いよね」、とか言って、安い酒で一日のアルコールの摂取量を賄っていたりする。僕ももう少し図々しくしてみようかしら。
ただ、太宰治は、『津軽』では図々しい酒飲みを、愛らしく描いているのだが、他の作品では「図々しい酒飲み」の「害悪」をしっかり描いている。特に、『親友交歓』なんかがそれだと思う。僕は太宰治の短編の中では『親友交歓』が一番好きだ。酒飲みに限らず、人間の図々しさが嫌なほど伝わってくる。ぜひ、『津軽』と併せて読んでみて欲しい。
これまでに挙げた作品に限らず、この記事を書くにあたって、「酒」をキーワードに太宰治の作品を読み返してみたのだが、いい描写が山ほどある。『津軽』の中で言えば、戦地を経験した「T君」と太宰が話すシーンなんてたまらない。
「戦地で一ばん、うれしかつた事は何かね。」
「それは、」T君は言下に答へた。「戦地で配給のビールをコツプに一ぱい飲んだ時です。大事に大事に少しづつ吸ひ込んで、途中でコツプを唇から離して一息つかうと思つたのですが、どうしてもコツプが唇から離れないのですね。どうしても離れないのです。」
凄まじい。痛ましく、かつ、気持ちのいい描写だ。
また、『人間失格』と『津軽』のほかにも、青空文庫で検索をかけて、太宰治の酒に関する文章を軽く漁ってみたのだが、そこで「禁酒の心」という文章を見つけた。5分もあれば読める長さなので、気が向けばぜひ読んでみて欲しい。僕は「配給」の時代を生きたことがないので、当時の詳しい酒事情はわからないが、それでも、常時共感しっぱなしの、とてもいい文章だった。
僕が特に好きだったのは、居酒屋の「おやじ」と「客」の力関係を描いた部分だ。
店へはいる。「いらっしゃい」などと言われて店の者に笑顔で迎えられたのは、あれは昔の事だ。いまは客のほうで笑顔をつくるのである。「こんにちは」と客のほうから店のおやじ、女中などに、満面卑屈の笑をたたえて挨拶して、そうして、黙殺されるのが通例になっているようである。念いりに帽子を取ってお辞儀をして、店のおやじを「旦那」と呼んで、生命保険の勧誘にでも来たのかと思わせる紳士もあるが、これもまさしく酒を飲みに来たお客であって、そうして、やはり黙殺されるのが通例のようになっている。…(中略)…けれどもお客も、その黙殺にひるまず、なんとかして一本でも多く飲ませてもらいたいと願う心のあまりに、ついには、自分が店の者でも何でも無いのに、店へ誰かはいって来ると、いちいち「いらっしゃあい」と叫び、また誰か店から出て行くと、必ず「どうも、ありがとう」とわめくのである。あきらかに、錯乱、発狂の状態である。実にあわれなものである。おやじは、ひとり落ちつき、
「きょうは、鯛の塩焼があるよ。」と呟く。
すかさず一青年は卓をたたいて、
「ありがたい! 大好物。そいつあ、よかった。」内心は少しも、いい事はないのである。高いだろうなあ、そいつは。おれは今迄、鯛の塩焼なんて、たべた事がない。けれども、いまは大いに喜んだふりをしなければならぬ。つらいところだ、畜生め! 「鯛の塩焼と聞いちゃ、たまらねえや。」実際、たまらないのである。
繰り返すが、僕は「配給」の時代を生きたことがないので、当時の酒がどれだけ貴重なものだったのかわからないが、それでも、居酒屋において「おやじ」にへつらうような感覚は、案外共感できるのもだ。
つい先日も、近所のもつ焼き屋に行った時に似たような気分を味わった。
その店はドリンクは口頭で頼み、肴は備え付けのメモ帳に書いて手渡すタイプの店だったのだが、ひとまず、目についた一品メニューだけを書いてメモを差し出すと、
「うち焼き物やなんで」
という一言とともに突き返された。
わけがわからず、5秒間ぐらい無言で見つめ合っていると、店主は、先に提供されていた僕の手元のアサヒの大瓶を指さして、「頼まないなら、それ飲み終わったら出てってもらっていいですよ」と続けた。
わお。
びっくりしたのと、相手の物言いにむかついたので、もう3秒ほど無言で見つめ合っていたのだが、さすがに見栄を切って帰る気にはなれず、突き返されたメモに、粛々と焼き物の名前を書いた(ちなみに、これで実際に頼んだ「れば」と「ちれ」がめちゃくちゃ美味かったのだから僕の完全敗北である。特に「れば」は、半生のプリプリとした食感で〈僕はよく焼いた、苦みと・歯の凹凸にこびりつくようなねっとりとした食感を楽しめるレバーも大好きなのだが〉、近所にこの店があって良かったと、思わざるを得なかった。結果として、「たん」と「かしら」と「こぶくろ」を追加注文して、大瓶2本とチューハイ2杯を飲んで帰った。酒飲みの立場は弱いものである)。
くだらない僕のエピソードトークで終わってしまったが、ひとまず太宰治の作品について書くのはここまでにしようと思う。本当は、太宰治の話から入って、いろんな作家の酒に関する描写を紹介していこうと思っていたのだが、太宰治の作品(それも、ほぼ『人間失格』と『津軽』)だけで、それなりの長さになってしまったので、ここで筆を擱く。確約はできないが、来月にはこの続きを書きたい。その時にもっといろんな作家の作品に触れたいと思っている。
僕は書き疲れたので、今日はひとまず終わりにして、例のもつ焼き屋にでも行ってきます。
文 献
- 太宰治(1950/1985/1996)親友交歓.青空文庫.https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/2271_34630.html
- 太宰治(1952/1985)人間失格.青空文庫.https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/301_14912.html
- 太宰治(1975/1989)禁酒の心.青空文庫.https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/284_34625.html
- 太宰治(1990)津軽.青空文庫.https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/2282_15074.html
- 川島航(2024)ステートメント_アルコール依存のケース🥃.In:zonbipo(編):ステートメント,3. https://note.com/96422/n/n48a9b973cd2f
- 坂口安吾(1948/1998)不良少年とキリスト
.青空文庫.https://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42840_24908.html