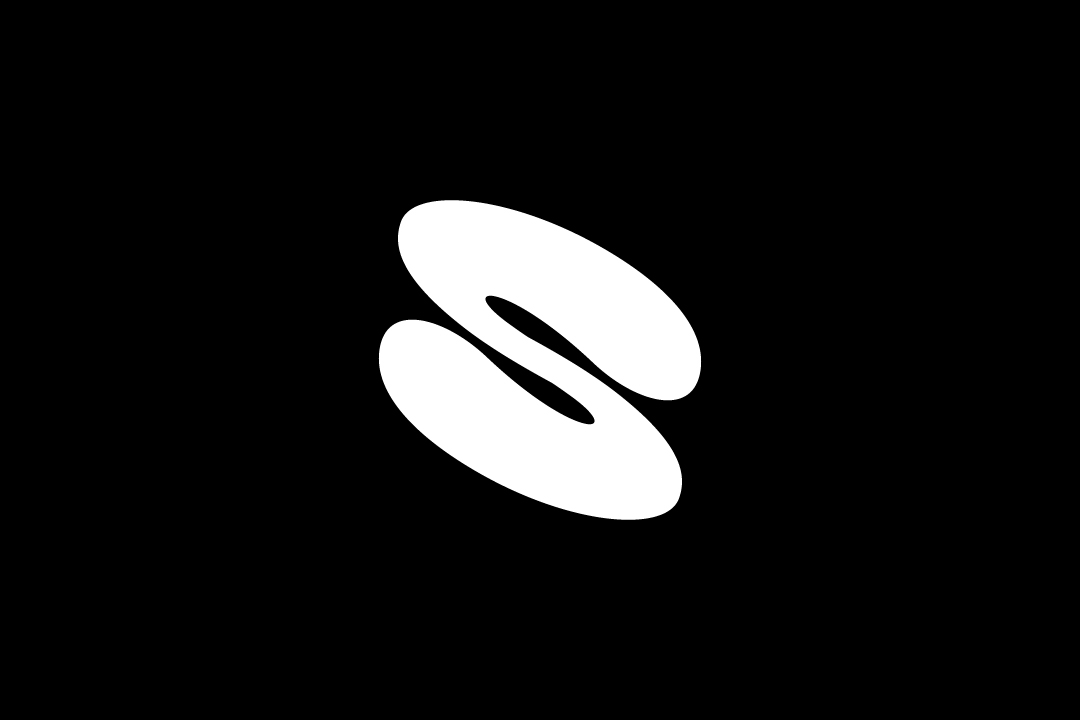- 「すべての美にして崇高なもの」へ─千石イエスとタイラー・ダーデン─
- エリ・エリ・レマ・サバクタニ─遠藤周作とイエス・キリスト─
- 多層構造のおとめたち─映画『ベネデッタ』と聖女カタリナ─
- 復讐者は賛美する─『復讐するは我にあり』─
この映画は、イタリアのカトリック修道女ベネデッタ・カルローニが、教会の聴罪司祭やみずからが属する修道院の院長に超自然的なビジョンを報告したことによる一連の騒動から、着想を得ている。
以下に、筆者がFilmarksに投稿した、当映画のレビューを登載する。
──「悪趣味。」
この映画は尼僧映画──“ナンス・プロイテーション(Nunsploitation)”というジャンルに分類される。ナンス・プロイテーション映画の多くは、修道院に身を置き、修道生活を実践する女性の情欲や業を題材として扱っており、この映画においてもそれは例外ではない。映画ライターのなかざわひでゆき氏は、ナンス・プロイテーション映画の定義を「抑圧」とし、ナンス・プロイテーション映画とはつまり「性的抑圧、社会的抑圧、精神的抑圧など、男性主導の父性社会で女性が受けてきた様々な抑圧を集約した」ものであると述べた。しかし、ナンス・プロイテーション映画の多くが、単なるポルノ映画──「男性からの性的な眼差しを拒む女性の、尊厳を貶め・性的に消費する」目的で作られたものであることを考えると、この定義に完全に同意することはできない。
この映画がほかのナンス・プロイテーション作品と異なるのは、女性をエンパワーメントする要素が含まれている点にある。この映画は、抑圧に抗い、みずからの知恵を武器にして権力を手に入れようとする女性の姿を描いているとも言える。
しかしながら、マリア像を張型に作り替え──聖書の中にそれを隠すなど、キリスト教の信徒にとって、ショッキングな描写が少なくないのも、ひとつの事実である。
ところで、2024年、パリオリンピックの開会式において執り行われた数々のパフォーマンスは、数々の議論を生んだ。「貴族たちを街頭に吊るせ」という歌詞の含まれる──サン゠キュロット版『サ・イラ』をオペラ調で、高らかに歌い上げるマリー・アントワネット。黙示録の『死の騎士』にも似た装いで、夜のセーヌ川を駆け上がり、生前には成し遂げられなかった、パリへの参上を果たすジャンヌ・ダルク。
なかでも一際、論議を呼んだのは──『最後の晩餐』をモチーフにしたパフォーマンスである1。そのパフォーマンスでは、ドラァグ・クイーンなど、マイノリティを中心とした複数人の出演者がレオナルド・ダ・ヴィンチによる聖画『最後の晩餐』を再現した。
このパフォーマンスは、ローマ・カトリック教会がこれまで差別を行うとともに、公の場から排除してきたものをエンパワーメントする目的で、行われたものと考えられる。しかしながら、件のパフォーマンスは、そのセンシティブな内容ゆえに、多数の──いわゆる“保守的な”団体からの抗議を受けることとなった。
8月3日、ローマ教皇庁は、バチカンが所持する公式メディア「バチカンニュース」を通じて、以下の声明を公表した。
「開会式の、いくつかの場面に対し、悲しみを覚えた。多くのキリスト教信者や、他の宗教の信者による不快感を嘆く声に、我々も加わらざるを得ない」
「全世界が共通の価値観のもとに集うイベントで、宗教的信念を嘲笑するような暗示はあってはならない」2
上記の声明からは、バチカンやローマ教皇が、あのパフォーマンスを自分たちキリスト教徒に対する“侮辱”と見なしたことがわかる。
確かに、あのパフォーマンスには、性的マイノリティを積極的に差別し排除するカトリックへのカウンター的な側面が含まれていたことは否定できない。
しかし、件のパフォーマンスが、多様性を称賛する目的で行われたものであることを考えると──。
要するに、これまでキリスト教が軽視してきた属性やその当事者、関係者をエンパワーメントすることを目的とした創作物の中には、結果的に聖書や信徒を傷つけたり、揶揄するものが少なくないということだ。映画『ベネデッタ』における過激な描写に対しても、同じことが言えるだろう。
この映画の中で描かれる宗教的象徴の扱いや、性的なテーマの取り扱いは、カトリック教会や信者にとって冒涜と感じられる部分もあるかもしれない。しかしながら、それは単に、挑発を意図したものではなく、長い間抑圧されてきた声や存在を可視化し、取り戻そうとする試みであるという点を意識することが大切であると言える。閑話休題。
劇中においてベネデッタは、みずからをキリストの花嫁・神の寵愛を受けた女として、数々の預言を行う。
幻視(ビジョン)をもとに、キリストとの婚姻関係を主張した女性といえば、まず思い浮かぶのはアレクサンドリアの聖カタリナのことだ。
アレクサンドリアの聖カタリナは、「聖人」として数えられることも多い、世界で最も有名な殉教者のひとりである。彼女の伝説は、時代・地域によって様々であるが、いずれにしても、彼女が「キリストの花嫁」を名乗り、またそれが理由で弾圧を受けたという点は変わらない。
ベネデッタとアレクサンドリアの聖カタリナ。この二人の奇妙な相似性は、映画がラストに近づくほど、顕著になっていく。
物語のクライマックス、ベネデッタは同性愛の罪により火刑に処される。しかし、炎が彼女を飲み込む寸前、民衆が彼女を救い出す。その姿はまるで、車裂き刑に処されそうになった聖カタリナが、稲妻や天使の手によって奇跡的に解放された瞬間を彷彿とさせる。
何が言いたいのかというと、つまり──ベネデッタのメイン・プロットは、聖女カタリナの伝説の一部を剽窃し作られたものだと言える。剽窃、というのは、いささか乱暴な印象を与えるかもしれない。しかしながら、聖カタリナの伝説が「信仰のために迫害された女性たちの記憶をもとに、作られた合成物3」である可能性が高いこと──そして、女性信徒に「規範」を示す目的で流布されたことを思うと、剽窃と言うより、致し方ない。
カトリック教会によって抑圧されてきた者たちに力を与えるために、世界で最も有名な創作聖女の伝説を巧妙に借用し、紡がれた物語──この映画は、ナンス・プロイテーションとしてだけではなく、このように捉え直すことができる。
ところで、さきほど話題に上げた聖女カタリナの伝説には、参照元──いわゆる「元ネタ」が存在していることはご存知だろうか。というのも、聖女カタリナの伝説は、5世紀初頭の哲学者「ヒュパティア(Hypatia)」の逸話をもとに作られた可能性が高いと言える。
「ヒュパティア(Hypatia)」は、男尊女卑的な風潮が数多く残る当時の東ローマにおいて、その高い見識と知識を武器に、数学や天文学、哲学など、様々な分野で功績を残した。また、ヒュパティアの講義には、時の権力者を含む、多くの人々が足を運んだ。これらのことからは、ヒュパティアが女性でありながら幅広い層から深い尊敬を集めていたことがうかがえる。
当時のアレクサンドリアは、多神教の信仰を持つ人々やユダヤ教徒、キリスト教徒が共存する、多様性に富んだ都市だった。神秘主義を否定し、異教の理性主義を擁護していたヒュパティアが人々からの尊敬を集めた背景には、このようなアレクサンドリアの特性が少なからず影響していたと考えられる。
しかし、380年にローマ帝国がキリスト教を国教に定め、392年にはほかの宗教の信仰を禁止したことで、その微妙な均衡は次第に崩れていった。かつて多様な信仰が共存していたアレクサンドリアは、急速にキリスト教中心の社会へと変貌を遂げる。そして、その変化の波は、ヒュパティアにも容赦なく押し寄せた。
415年、ヒュパティアはキリスト教徒の手によって命を奪われた。当時のアレクサンドリアでは、キリスト教徒とユダヤ教徒の間で激しい対立が起こっていたこと、その中で、ユダヤ教徒側の指導者(と、見なされていた)ローマ提督オレステスと、ヒュパティアが親しい関係にあったこと、この二つの要素が複雑に絡み合ったことによる悲劇だと言われているが、実際のところは、どうだかわからない。
聖女カタリナの伝説は、ヒュパティアの死後に、キリスト教徒が彼女の逸話を基に創作したものだと言われている。その背景にはいくつかの説が存在する。ヒュパティアの殺害によって傷ついた教会の名誉を回復するためという説もあれば、あるいは、密かにヒュパティアを慕っていたキリスト教徒が、彼女を聖人のように描きたかったからという説もある。
いずれにしても、聖女カタリナの伝説は、ヒュパティアの信念や信仰を無視し、彼女の生涯から都合の良い部分だけを取り出して作り上げられた物語──ということになる。
聖女カタリナの伝説、映画『ベネデッタ』、このふたつはいずれも──対立する立場やイデオロギーを持つ人物から、都合の良い要素や物語を取り込んで作り上げられたものである。
これらのことからは、自分たちの価値観や信仰と相反するイデオロギーを持つ人物から、都合の良い要素だけを抜き出して剽窃し、都合よく改竄するという性質が、人間全体に普遍的に存在するものだということがわかる。
この映画『ベネデッタ』は、私たちに多くの問いを投げかけている。私たちが信じるものは、本当に誰のためのものなのか。それを改竄し、再解釈してきたのは誰なのか。
最後に、以下の文章をもって、この論考を締めくくりたい。
「だれでも、持っている人は更に与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。(マタイによる福音書 25:29 新共同訳)」
脚 注
- ここでは、件のパフォーマンスの参照元を「最後の晩餐」と言い切っているが、開会式の芸術監督を勤めたトマ・ジョリ氏は、各キリスト教系団体からの抗議を受け、該当パフォーマンスと「最後の晩餐」の関係性を否定している。https://www.sankei.com/article/20240804-KPFMY22SAJGPRJG7LZBI3LOKZA/?outputType=theme_paris2024 ↩︎
- 原文は以下の通り。
「パリ・オリンピックの開会式のいくつかの場面に悲しみを覚えると共に、ここ数日上げられていた、多くのキリスト教信者や他の宗教の信者にもたらした不快感を嘆く声に加わらざるを得ない/全世界が共通の価値観のもとに一致して集う信望ある催しにおいて、多くの人々の宗教的信念を嘲笑するような暗示はあってはならないはずだ/表現の自由は、当然問題ではない/他者の尊重においては限界がある」https://www.vaticannews.va/ja/pope/news/2024-08/comunicato-santa-sede-cerimonia-apertura-olimpiadi.html ↩︎ - Christine, W.(2007)The cult of St Katherine of Alexandria in early medieval europe. Routledge. https://www.routledge.com/The-Cult-of-St-Katherine-of-Alexandria-in-Early-Medieval-Europe/Walsh/p/book/9780754658610 ↩︎