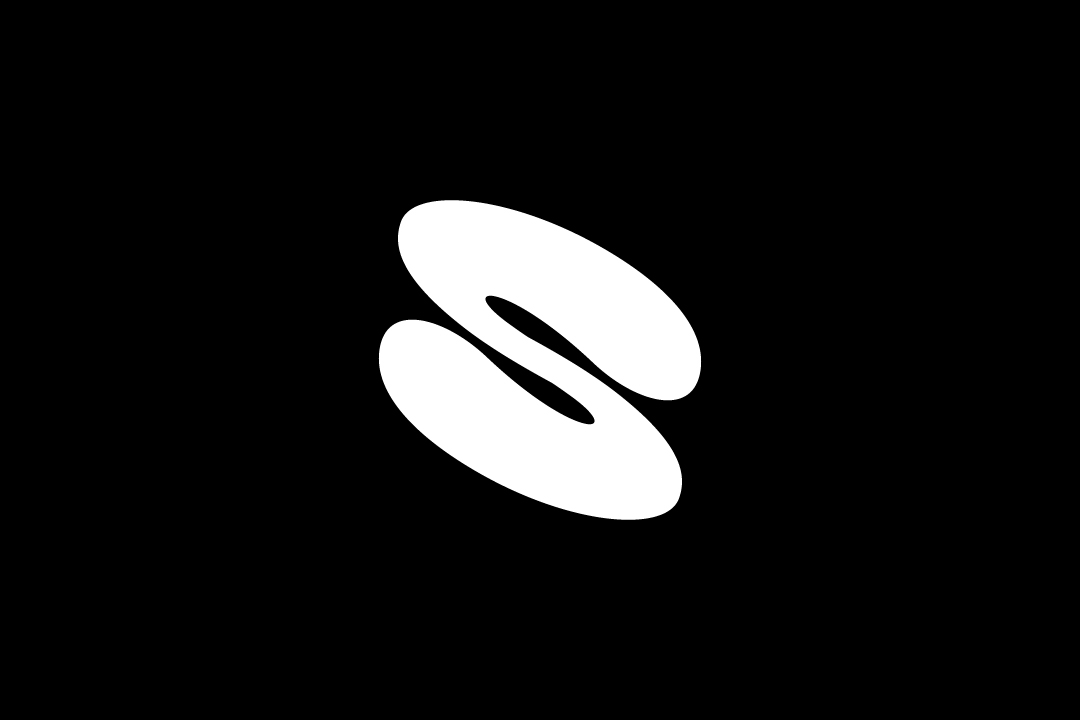- 「すべての美にして崇高なもの」へ─千石イエスとタイラー・ダーデン─
- エリ・エリ・レマ・サバクタニ─遠藤周作とイエス・キリスト─
- 多層構造のおとめたち─映画『ベネデッタ』と聖女カタリナ─
- 復讐者は賛美する─『復讐するは我にあり』─
そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と言われた。それは「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という意味である1。
第1回の記事の中で、筆者は、日本のキリスト教徒が歩んできた閲歴を以下のように総括した。
「我が国において、キリスト教徒は長きにわたり迫害されてきた。日本におけるキリスト教徒の歴史とはすなわち、迫害の歴史である」
江戸幕府が1587年に発布した「伴天連追放令」および、これに端を発する宗教的弾圧──通称「切支丹狩り」は、少なくとも数百名ものキリスト教徒を冥府の底に追いやったと言われている。
多くの者は幕府の役人によって『転ぶ』こと──つまり改宗を強要された。それでも『転び』を拒んだ者たちは、『水責め』や『穴吊り』といった残酷な方法で処刑された。
これらの残酷な所業は「排耶論」を徴憑としている。
当時の日本においては──「西洋諸国はキリスト教によって人々の心を誘惑し、それを侵略のための手段にしている」2といった内容の「排耶論」を内面化する者が少なくなかった。
これらの論理と、それに基づいて書かれた『排耶書』は、日本人のキリスト教やその信徒に対する偏見をさらに強める役割を果たした。1873年に禁教令が撤回された後も、これらの事物によってもたらされた偏見が消えることはなかった。
例えば、1942年には、ホーリネス教会を母体とする日本聖教会およびきよめ教会に属する教職員96名が、「治安維持法違反」の名目で不当に逮捕されている。
このような出来事の数々は、日本を「神なき国」にするのに、十分なものだった。
ホルスト・ゲオルク・ペールマンHorst Georg Pöhlmannいわく、ギュンター・グラスの『ブリキの太鼓』におけるイエス像の描写は、「多くの現代人にとって、教会のイエスは、もはや自分たちの生活となんら関係のない、“死んだ遺産にすぎないこと”」3を示しているという。
これは遠藤周作の作品『侍』におけるキリスト像の描写においても、同様のことが言える。
「醜い痩せこけた男、威厳もなく見ばえもせず、ただただみすぼらしい男、利用したあとは棄てるためにある男、見たこともない土地に生れ、すでに遠い昔に死んでしまった男と自分とはなんの関わりもないと侍は考えた」4
『侍』の主人公・長谷倉六右衛門がモノローグで『侍』と表記されるのはなぜか。それは、彼が当時の日本人を象徴する存在だからにほかならない。つまり、『侍』の作中におけるイエス像の描写は、日本人の心が神から遠く離れていることを示していると言えるだろう。
いわく、アーサー・ケストラーは、自著の中で、日本人の倫理観について、以下のように綴ったという。「日本の倫理規範は、相対的かつ状況的である」
遠藤周作は、この原因を、日本が「神なき国」であることに求めた作家のひとりである。例えば、氏の代表作である『海と毒薬』は、1945年に発生した「九州大学生体解剖事件」をモデルとした生体解剖事件、これに携わることになった日本人一人ひとりの小市民性を描くことで、日本人の倫理観がいかにもろく──揺らぎやすいものなのかを示した。
彼は、「神」──確固たる指標を失った日本を憂慮していた。それと同時に、信徒がそのような状況に置かれてもなお、神が沈黙を貫く意味を模索し続けてもいた。彼は、数々の作品を通じて、神に叫び続けているのだ。「エリ・エリ・レマ・サバクタニ」──我が神、我が神、どうして私たちをお見捨てになったのか! と。
『沈黙』および『侍』は、氏が思索の果てにたどり着いた、ひとつの結論を、表している。
──例えば、『沈黙』の本編は以下の文章をもって締めくくられている。
「自分は…(略)…あの人を決して裏切ってはいない。今までとはもっと違った形であの人を愛している。私がその愛を知るためには、今日までのすべてが必要だったのだ。…(略)…そしてあの人は沈黙していたのではなかった。たとえあの人は沈黙していたとしても、私の今日までの人生があの人について語っていた」5
また、『侍』のストーリーは、解説の中で、以下のように総括される。
「長谷倉と仲間の武士たちは、肉体の世界で打ち負かされ、屈辱をうけ、失敗者として日本に戻ってくる。だが長谷倉が、絶望と、おそらくは死の深淵の前に立つとき、彼の傷をいやすことのみを求める王、みずからもまた『人々から軽蔑され、拒まれ』てきた王その人であった」6
つまり、潜伏キリシタンをはじめとする日本のキリスト教徒たちが、父なる神の沈黙によって命を失ったのは、『歴史の敗者』であるイエス・キリストの苦痛を、実感をもって理解し、その隣人となるためだと氏は結論づけたのである。神の沈黙、すなわち父なる主の沈黙によって糾弾され、処刑されたイエス・キリストと、その苦痛を分かち合うためには、自らも彼と同じ苦境に立つしかなかった、と。
しかし、イエス・キリストは“貧しいものたち”のための神である。イエスがほかの預言者と決定的に異なるのは、彼が、自身を貧しい人々の隣人として位置づけた点にある。また『貧しさ』とは何も、物質的な貧しさ・経済的な貧しさだけをいうのではない。ペールマンいわく『この貧しい人々の中には、…(略)…悩む者や抑圧されている者、病人、そして社会的に罪を負う者たちも含まれていた』7という。
ところで、現代において、この条件に当てはまらない、つまり悩みがなく、社会的抑圧も受けず、健康で、社会的に罪のない人間がどれほどいるだろうか? 筆者は考える──人は、生まれながらにして主の、イエス・キリストの隣人であると。
かといって、潜伏キリシタンをはじめとした日本のキリスト教徒たちが、虐げられ、命を落としたのには、なんの意味もなかったのかというと、そうではない。
例えば、パウロ書簡のひとつ、コリントの信徒への手紙には、以下のような一節がある。
わたしたちが語るのは、隠されていた、神秘としての神の知恵であり、神がわたしたちに栄光を与えるために、世界の始まる前から定めておられたものです8。
言い換えれば、この世で起こるあらゆる出来事は──すべて神の計画の一部であり、人間が生まれるはるか以前から定められているということになる。
つまり、日本のキリスト教徒たちが経験した迫害も──その一環であると言えるだろう。
では、なぜ神は日本のキリシタンに、このような試練を課したのか。
遠藤周作氏はたびたび、神を存在としてではなく、働きとして捉えるべきだと語っている。彼のこの考え方を端的に表す文章として、以下のものがある。
「たとえばもしあなたが、私がいままで話してきたことを聞いて、キリスト教に興味を持ち、やがて洗礼を受けたとすると、神は…(略)…私という者を通してあなたに働きかけたことになる」9
迫害を受けたキリシタンたちに対しても、同様に考えることができる。神は、彼らの苦しみや犠牲を通じて──信仰の意味と、信仰を貫くことの高潔さを示したのだ。
例えば、筆者の祖先であり、先にあげた『侍』のモデルでもある、支倉六右衛門常長(以下、支倉常長)の生涯は、ある一定の価値観を内面化した人たちにより、「無為なもの」とみなされることが多い。
1613年、仙台藩初代藩主伊達政宗は、フランシスコ会所属の宣教師ルイス・ソテロの仲介のもと、家臣の支倉常長を大使としてスペイン・ローマへ派遣した。後に「慶長遣欧使節」と呼ばれるこの使節団の差遣は、幕府の認可の上で行われた、一大事業であった。しかし、彼らの7年におよぶ航海の日々は、外交的にも文化的にも、何も成果をもたらすことはなかった。
というのも、一行が帰国するまでの間に──日本においては、前述の禁教政策が、急速に──それこそ、驚くべきスピードで進行していた。東北においても、これは例外ではなく──支倉常長の帰国から3年後の1623年には、仙台城のすぐそばを流れる広瀬川において、イエスズ会神父カルバリヨら9名のキリシタンが水責めに処された記録が残っている10。また、伊達政宗が支倉常長が仙台に帰着した2日後に、キリシタン禁令の札を立てたとする学者も少なくない11。そのような状況下で、ある議題が宣教師たちの間で大きな論争を引き起こした。それは、支倉常長がマドリードでエスパーニャ国王フェリペ3世の列席のもとで洗礼を受けた事実に関するものだった。洗礼名は「ドン・フィリッポ・フランシスコ・ハセクラ(Felipe Francisco Faxicura)」。つまり──帰国後間もなく病で亡くなった常長が、この信仰を最後まで守り抜いたのかどうかが、人々の関心を集めたのである。
しかしながら、これについては、常長当人は、信仰を保持した可能性が高いと言えるだろう。というのも、慶長遣欧使節の手引きをした、フランシスコ会の宣教師、ルイス・ソテロ氏は、教皇グレゴリウス15世に対して、以下のような内容の手紙を出している。
「もう一人の大使であるわが同僚フィリッポ・ファシクラは国王のもとに戻って、国王から大いに表彰されました。かくの長旅による疲労を回復するために、自分の所領で休養し、妻子や家の者を家来とともにキリスト教徒となし、多数の血族や縁者の地位ある家臣にも説きました。ところで、帰国後一年にもならないうちに、あらゆる感化と模範を示して、敬虔のうちに死去しました」12
現に、彼が逝去してからもしばらくの間は、キリスト教徒の姿を顕わにする『支倉常長像』や異教徒の国の市民権や貴族位を保証する『ローマ市公民権証書』が保管されていた。また、この頃、支倉家において保管されていた祭服や、礼拝のための聖画、聖具類の一部には、使用された形跡が少なからず見受けられる。つまり、支倉常長は──ルイス・ソテロが手紙の中で語ったように、「敬虔のうちに死去」したということになる。
彼の死後、しばらくの間、支倉家ではその信仰が受け継がれていたようであるが──しかし、支倉家の使用人数名が信仰を理由に処刑され、さらに家長である常長の実子・常頼もその煽りを受け、処罰されたことを機に、信仰は断絶したものと思われる。
前述の通り筆者は、支倉常長の、遠縁の子孫にあたる。しかしながら、筆者が親などから、信仰にまつわる教育を受けたことは一度としてない。筆者は16歳の時、偶然、信仰と出会った。
一部の方は、筆者と親との関係があまり良好ではないことをご存じかもしれない。もし信仰がそのような関係にある親から受け継いだものであったならば、筆者はこれを大切に思うことはできなかったであろう。また、このように、信仰を文章として綴ることもなかったに違いない。つまり、私がニュートラルな状態で信仰と巡り会えるよう、主がその道筋を整えてくださったのだとも言える。
物語をどのように捉えるか──これが、問題だ。
脚 注
- マタイによる福音書 27:46 口語訳. ↩︎
- 鬼束芽依(編)(2024)創られたキリシタン像─排耶書・実録・虚構系資料 西南学院大学博物館研究叢書.西南学院大学博物館,p.20. ↩︎
- Pöhlmann, H. G.(1976)Wer war Jesus von Nazareth? Gütersloher Verlagshaus.(秋山卓也(訳)(1984)ナザレのイエスとは誰か.新教出版社,p.19.) ↩︎
- 遠藤周作(1986)侍.新潮社,p.299. ↩︎
- 遠藤周作(1981)沈黙.新潮社,p.296. ↩︎
- 遠藤周作(1986)侍.新潮社;Van C. Gesselによる解説:pp.496-497. ↩︎
- Pöhlmann, H. G.(1976)Wer war Jesus von Nazareth? Gütersloher Verlagshaus.(秋山卓也(訳)(1984)ナザレのイエスとは誰か.新教出版社,p.134.) ↩︎
- コリントの信徒への手紙一 2:7. ↩︎
- 遠藤周作(1983)私にとって神とは.光文社,pp.20-21. ↩︎
- 工藤隆哉(2020)支倉六右衛門常長の最期─帰朝四百年の謎.金港堂,p.249. ↩︎
- 佐々木徹(2013)伊達政宗と慶長遣欧使節─大洋の向こうに見た夢.In:仙台市博物館:慶長遣欧使節出帆400年・ユネスコ世界記憶遺産登録記念特別展 伊達政宗の夢─慶長遣欧使節と南蛮文化. ↩︎
- 濱田直嗣(2012)政宗の夢常長の現─慶長使節四百年.河北新報出版センター,pp.261-262. ↩︎