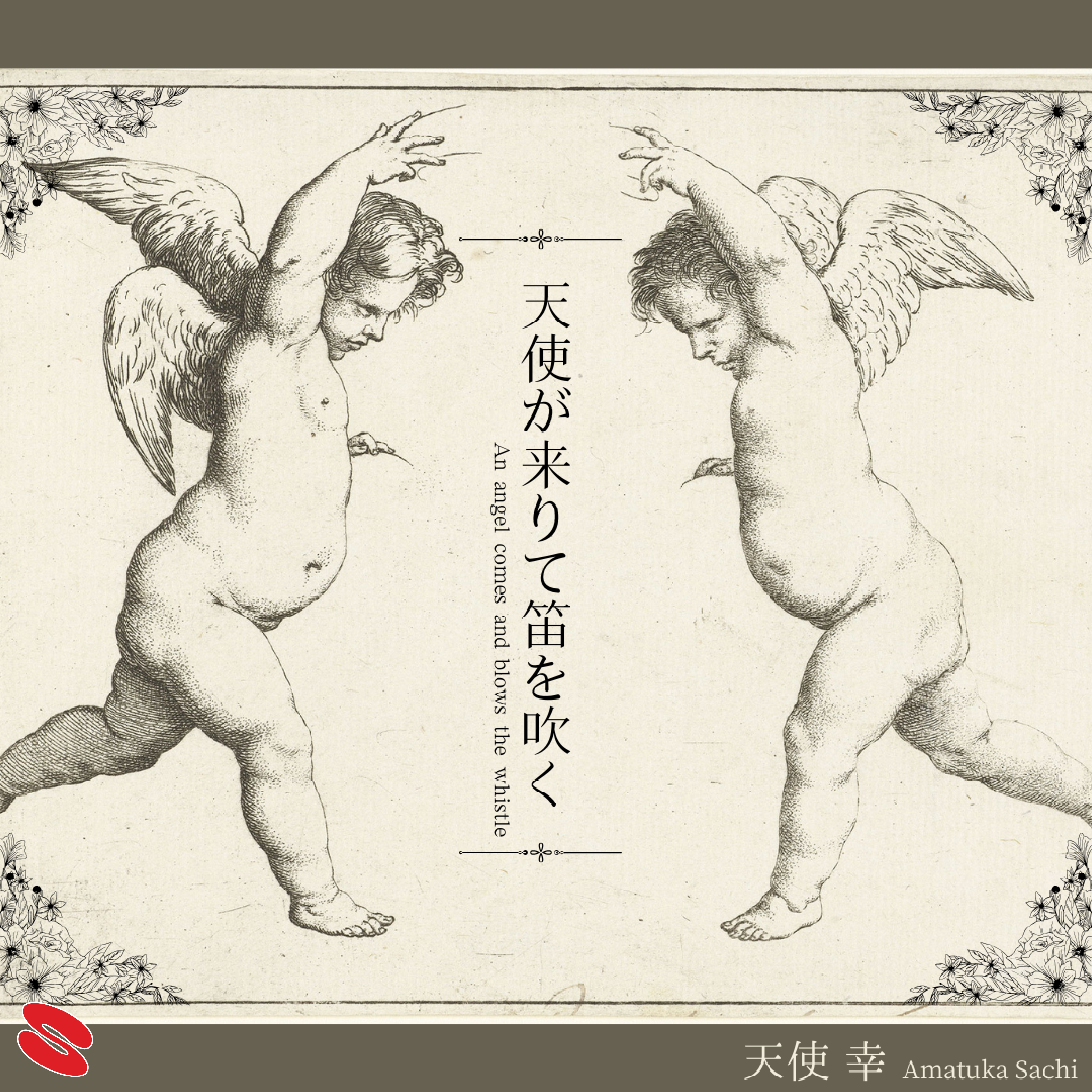- 「すべての美にして崇高なもの」へ─千石イエスとタイラー・ダーデン─
- エリ・エリ・レマ・サバクタニ─遠藤周作とイエス・キリスト─
- 多層構造のおとめたち─映画『ベネデッタ』と聖女カタリナ─
- 復讐者は賛美する─『復讐するは我にあり』─
前回の記事では、「日本のキリスト教徒がどのような弾圧を受けてきたか」を、慶長遣欧使節の中心人物、支倉常長を中心に、概説した。しかし今や、弾圧を受けているのはキリスト教徒だけではない。現代の日本において、信仰を内面化するもの、ひいてはこれを生活の中で実践するものは、それを行ってないものたちによって、冷笑ないしは嘲笑を受けることとなる。昨今の日本、とりわけSNSを中心に「宗教フォビア」とでも呼ぶべき風潮が形成されつつあることを、否定することはできない。
2025年、文部科学省が東京地裁に提出した「家庭連合(旧統一教会)に関する陳述書」には、一部、事実に基づかない記述が含まれていた1という。しかし、これに対して十分な精査や批判が行われたかというと、そうではないだろう。家庭連合(旧統一教会)が、ある特定の年代に、いささか行き過ぎた霊感商法を行っていたことは事実である。だからこそ、批判・糾弾はフェアな方法で行わなければならない。
この事例からもわかるように、現在、日本を跋扈する「宗教フォビア」の煽りを最も強く受けているのは──第二次世界大戦後に全国的に教勢を拡大した、新興宗教である。なかには、件の「宗教フォビア」は、オウム真理教と──彼らが1995年に引き起こしたテロ事件によって形成されたものなのだから、排斥もやむを得ないと考える人もいるだろう。
しかし、千石剛賢を主宰とする「イエスの方舟」の事例においては、どうだろうか。イエスの方舟は、キリスト教系の団体で、「『他人を他人と思わず、他人を自分と思う』ことにより『自愛』をむしろ信者たち相互の中に分散し、さらにこれをイエスの隣人愛の中に統合した2」教義が、他の団体と一線を画していたこともあり、若い女性が数多く、その活動に参画していた。
しかし、1980年代に入ると、「イエスの方舟」は女性向け週刊誌などのマスメディアを中心に、激しいバッシングを受けることになる。というのも「イエスの方舟」は、前述の「隣人愛」を恒久的に持続させるため、共同生活を営み、さらにその拠点を「漂流」と称して、定期的に移動していた。この独特な生活様式に対し、信徒の家族の中には不安や反感を抱く者も少なくなかった。これらのひとびとは「イエスの方舟の教祖・千石イエスに娘が誑かされている」という旨の主張を展開するようになる。──「イエスの方舟」が「若い女たちを惑わせ、翻弄する、いかがわしい団体」として、世間から疑いの目を向けられるようになったのは、このような経緯からである。
教祖・千石が出頭し、不起訴処分となったのは1981年。オウム真理教がテロ事件を起こす14年前にあたる。
このことから、日本における宗教に対する恐怖や偏見、いわゆる「宗教フォビア」がオウム真理教によって生まれたという見方は、一部正しいとも言えるが、一方でそれ以前から存在していたことも事実である。
では、件の「宗教フォビア」はどのように形成されたものなのか。
ヴィルヘルム・ライヒWilhelm Reichは、自著『キリストの殺害』において、人間は生まれながらにして「わな」に囚われており、その「わな」の中では「力強く生きること」は、極めて困難だと主張している。
そして、この理論を基に、キリストが殺害された理由について次のように詳述している。
「わなのそと、すぐそばに、生きている生命が、あなたをとりまいている目にみえるすべてのものに、耳にきこえるすべてのものに、鼻がかぐすべてのものにある。わなのなかの犠牲者にとって、それは永遠の苦痛であり、タンタロスの誘惑なのだ。あなたは、それを見る、それを感じる、そのにおいをかぐ、あなたは永遠にそれにあこがれる。しかも、あなたはぜったいに、ぜったいに出口をとおってわなのそとへでることはできない。わなのそとへでるなど、おもいもよらないことになっている。それは、ただ夢と詩と偉大な音楽と絵画でしかえることができず、あなたじしんの運動力ではもはやできない。出口へのカギは、あなたじしんの性格のよろいのなかと、あなたの体と魂の機械的硬直の中に、セメントづけにされている。
これが、大いなる悲劇だ。…(略)…
もしも、あまりながいこと暗い地下室でくらしていたら、あなたは日光をきらうようになるだろう。光を感じるべき目の能力をうしなうことさえあるだろう。ここから、日光に対する憎しみがくる。
…(略)…
しかしながら、幸福なくらしとわなにかかるまえのとおいむかしの幸福な生活の記憶にたいするふかいあこがれは、のこっている。しかし、あこがれとか記憶は、ほんとうの生活においては実現できない。そこで生命に対する憎しみが、…(略)…生じる3。」
つまり、自らが決して手に入れられない「すべての美にして崇高なもの」に対する憎悪が、そのまま「すべての美にして崇高なもの」と相似した──すなわち、宗教的なもの、神秘的なものへの憎悪へと転化したのだと、ライヒは主張しているのだ。
しかし、これだけでは十分な説明とは言えない。「宗教」という言葉が、自らと異なる意見や思想を持つ人々を揶揄する目的でしばしば使用されることが、そのことを雄弁に示している。ところで、そもそも「宗教」という言葉の定義は、果たして十分に検討された、と言えるだろうか?
荒井献は『聖書のなかの差別と共生』において、「宗教」という言葉の定義について次のように詳述を行なっている。
「──宗教とは『共同性の崩壊を前提とし、世俗を超えた“聖なるもの”を要とする新しい共同性に自己を再統合しようとする心のはたらき』とでもいえようか4。」
「宗教は「聖なるもの」との出会いによって引き起こされる、不条理経験を否定的に媒介した共鳴経験をその核とする。「聖なるもの」は元来両義的であり、それは「恐るべきもの」(tremendum)であると同時に「魅了するもの」(fascinans)であるが、前者がこれと出会う者に「不条理経験」を、後者が「共鳴経験」を引き起こすといえよう。前者は「聖なるもの」の超越的局面、後者はその内在的局面であるともいえる。「聖なるもの」はその超越的局面でそれに出会う者を崩壊しつつある共同体から切り離し、内在的局面で彼を新しい共同性に同一化させる、ということになろう5。」
例えば、前述のイエスの方舟は、自他の境界を意図も容易く侵襲してくる、いわば近親姦的な性質を持った、家族という共同体から、自らの意思を持ってして脱却することで、共同性の喪失を経た少女たちが、千石と、彼が説く教義を要とした新たな共同体に自らを統合したのだと、説明することができる。
信仰の原体験を描いたものとして、たびたび名前の挙がるアリ・アスター監督の2019年の映画『ミッド・サマー』の主人公、ダニーは、家族という共同体の崩壊を受けて、アニミズムという「世俗を超えた聖なるもの」を要とする新しい共同体──ホルガ村に、自己を再結合したことになる。
ところが、このような崩壊しつつ共同性から脱却し、新たな「世俗を超えた聖なるもの」を軸とする共同体に自己を再統合しようとする心の働きは、「弱さ」とみなされてしまう。
さりとて、マズローの欲求5段階説が示すように、所属欲は、人間の根源的欲求のひとつである。このことを考えると、所属欲と関連性の高い、件の心の働きを「弱さ」として切り捨てるのは、あまりにも、乱暴ではないだろうか。
例えば、チャック・パラニュークChuck Palahniukによって1996年に発表された小説、およびそれを原作とした映画『ファイト・クラブ』の登場人物の多くは、騒乱計画(プロジェクト・メイサム)という名の破壊活動に参画している。騒乱計画がどのようなものであるか、その概要が作中において明確に語られることはない(その最終的な目的が「資本主義の打倒」であることは示唆されるが、それがどのような経緯で普及していったのか、この目的を誰が理解していて、誰が理解していなかったのかは明白ではない)。しかしこれは、計画の参加者においても同様である。彼らの多くは──何もわからないまま、犯罪まがいの行為に身を染めている。彼らをそのような行為に駆り立てるものは何か──それは彼らが、タイラー・ダーデンの信奉者であり、ファイト・クラブの一員だからにほかならない。前述の「聖なるもの」の定義に、ファイト・クラブの主宰、タイラー・ダーデンは、恐ろしいほど当てはまっている。タイラー・ダーデンは、ファイト・クラブの参加者に「物質至上主義からの脱却」と、「唯物論的な価値観の構築」を求める。繰り返しになるが「聖なるもの」はその超越的局面でそれに出会う者を崩壊しつつある共同体から切り離し、内在的局面で彼を新しい共同性に同一化させる。つまり、ファイト・クラブとはタイラー・ダーデンという「聖なるもの」を要とした、ひとつの宗教であると言える。
では、ファイト・クラブの参加者たちは「弱い」のだろうか? ──多くの人は、この問いに対してNOと答えるはずだ。つまり、「聖なるもの」を中心とした共同体に自らを結びつけ、その中に身を委ねることを単純に「弱さ」と結論づけるのは、短絡的だとわかる。
所属欲求──あるいは「美しさや崇高さ」に近づこうとする心──は、彼らを「聖なるもの」へと強く引き寄せる。筆者が伝えたいのは、この「美しさや崇高さ」に惹かれる心こそが、決して否定されるべきものではないということだ。
ライヒもまた、こう述べている。
「生命の意味について哲学を展開しても、生命とはなにかを知らないかぎり、無益だ。そして、神は生命であり、それはすべてのひとに共通の、たしかな直接的な知識だから、じぶんがつかえているものを知らずに神を求めようとしたり、つかえようとしても、ほとんど役にたたない。
…(略)…
牢屋からぬけ出すには、まずとらえられているということを自覚しなければならない。わなとは人間の感情の構造であり、かれの性格の構造なのだ。わなから出るためにはわなを知り出口を見つけることしかないとしたら、わなの性質についての思想体系をかんがえだしても、ほとんど役にたたないのだ。それいがいのすべては、完全に無用だ。わなのなかの苦しみについて賛美歌を歌うとか、これはどれい時代のニグロがやった。わなの外のうつくしさについての詩を、わなのなかで夢見ながら書くとか。わなのそとでの生命を死後に約束するとか、これはカトリック教が信徒に約束していることだ。あきらめた哲学者のように、「つねに証拠不十分」と告白するとか。わなのなかの生活の絶望のまわりに哲学体系をつくるとか、これはショーペンハウアーのやったことだ。わなのなかの人間とはぜんぜん異なった超人を夢みるとか、これはニーチェがやったことだ。
…(略)…
最初にするべきことは、わなからの出口をみつけることだ6。」
つまり──「わな」から抜け出すことによってはじめて、人間は、「生きる」ことができるのである。自分の本来の生命を取り戻そうとすること──幸福を手にしようとすることは、決して、弱さではないし、恥ずべきことでもない。
最後に、以下の聖句を持って、当記事を締めくくりたい。
神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それは、すべての人を憐れむためだったのです7
脚 注
- 文部科学省が東京地裁に提出した陳述書には、家庭連合(旧統一教会)による霊感商法に関連する「被害総額」が記載されている。しかし、この被害総額に対する検証や精査の不十分さについて、一部の関係者や専門家からは批判の声が上がっている。https://www.worldtimes.co.jp/japan/20250203-190732/ ↩︎
- 荒井献(1999)聖書の中の差別と共生.岩波書店,p.21. ↩︎
- Reich, W.(1953)The murder of Christ: The emotional plague of mankind. WRM Press.(片桐ユズル・中山容(訳)(1979)キリストの殺害 W.ライヒ著作集4.太平出版社,p.24-25.) ↩︎
- 荒井献(1999)聖書の中の差別と共生.岩波書店,p.18. ↩︎
- 荒井献(1999)聖書の中の差別と共生.岩波書店,p.29. ↩︎
- Reich, W.(1953)The murder of Christ: The emotional plague of mankind. WRM Press.(片桐ユズル・中山容(訳)(1979)キリストの殺害 W.ライヒ著作集4.太平出版社,p.20-21.) ↩︎
- ローマの信徒への手紙 11:32 ↩︎